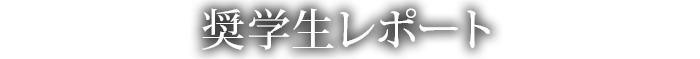
人を溶かすような暑さから逃れること二度目の夏。私は文明の利器(エアコン)を代償に、涼やかな日々を過ごしています。早いもので、もう八本目の奨学生レポート。ぼんやりと締め切りに急かされながらローマ字配列のキーボードに指を走らせるのもあと二回だけと思うと、感慨深いような、寂しいような気持ちです。
せっかく四ヶ月もの長い休暇があったのですから、構成や内容の練りようもあったのでしょう。が、もうこの留学生活も折り返し地点を過ぎてしまったというのに、時間がある、というだけの理由で、これまでの形式を変えるのは性に合いません。直近のレポート通り、前半-後半構成で私の一年と感じたことをここに記録し、振り返っていけたらなと思います。
UCLでは、学年を修了するために一年で120 credits分の授業を取る必要があります。今年度は哲学から4単位(60 credits)、美術史から4単位(60 credits)を取得しました。なかなか馴染みのない授業も多い(気がする)ので、それぞれの授業についてさっくりとまとめていきます。
( Term 1 )
Art and Object:
「ものの見方」について主に取り扱った授業でした。週ごとに講演してくださる教授が変わり、学期終わりにはObject Response Essayという選択した作品について小論文を書く課題がありました。目に映るものに対してどうアプローチするか、そんな大きなテーマがコースの中心のためか自由度が高く、とても愉しかったです。この課題を通して、自分の興味が歴史としての美術史ではなく、哲学(美学)寄りの美術史なんだな、ということを再確認することができました。来年の授業に美学Aestheticsがあり、今から楽しみです。
Art History Survey (1):
古代インドの遺跡からビザンチン美術、遠近法の発明まで、美術史をつまみ食いしていくような授業でした。美術史に触れたことがなく、専門をまだ絞る前の学生に美術史の幅広さを伝えるためのコースなのかなと愚考しつつも、扱う内容があまりにも飛び飛びで、レクチャー同士の繋がりを見出すことに苦労しました。歴史という織物を学びにきたのに、何万本と使われた糸の中の、ごく僅かな繊維しか見せてもらえなかったような気分です。セミナー内や先輩からも同じ意見が多く、複雑。ただ、一年生のうちに、これまで全く踏み入れたことのなかった分野に触れられて良かったのかな、とも思います。
Ancient Greek Philosophy:
今年度、一番苦戦を強いられたと言っても過言ではない古代ギリシャ哲学。片面にギリシャ語、もう片面に英語訳(しかも結構かため)の課題図書を一目見て圧倒されてからというもの、なんとなく苦手意識を持ってしまい、なかなか文章が頭に入ってきませんでした。担当の先生が「初めの3週間でやる内容が一番難しいからね〜」とおっしゃっていた通り、その期間に学んだプラトン以前の思想については、今でも人にうまく説明できるか自信がありません。普段私たちが当たり前に捉えている、意識して考えることもしない「もののあり方」がまだ発見されていなかった時代に人はどう物事に説明をつけていたのか。古い年代の書物を読む上では当然のことかもしれませんが、かつての考え方を「古い、無知だ」と一蹴せず、建設的に批評することの難しさを実感しました。
Philosophical Study Skills:
前回のレポートでも紹介した、私にとっての天国です。Aレベルで哲学をやっていた頃からOntology(存在論)やEpistemology(認識論)が好きで、美学が好きで、不条理文学が好きで、そんな好き要素しか詰まってないコースでした。扱うトピックはランダムに割り振られてしまうので、自分の運に泣いて感謝するしかありません。
( Term 2 )
Art and Object:
Term 1に受けたArt and Objectと同じコースです。二学期にわたって開講されました。「どう見るか」が授業の中心だったTerm 1に比べ、「どう発信するか」に重きが置かれた授業だったかなと思います。プレゼンとポートフォリオ制作など、エッセイ以外の課題で評価されるのが珍しく、成績も納得のいくものが取れたので嬉しかったです。
Art History Survey (2):
こちらもTerm 1に受けたArt History Survey (1)の続きです。基本的には(1)と同じような形式の授業でしたが、取り扱った年代がルネサンス以降でしたので多少とっつきやすかったです。テストにオノ・ヨーコが出てきたことを除き、取り立てて触れることもないので割愛いたします。
Early Modern Philosophy:
最初の五週間は講義、セミナーともに一切のIT禁止。そう書かれたコース概要を見てまず、度肝を抜かれました。大学に入ってから全てのノートをパソコン上で取っていた&全ての読書課題をオンラインで読んでいたもので……しかし考えてみれば、19年の人生の中、アナログでノートを取っていた時代の方が圧倒的に長いのですから不思議な話です。陳腐ですが、利便性と引き換えに失ったものを少し取り返した気分でした。だがしかしやはりパソコンは便利。五週間の禁止期間が明けるとすぐにOneNoteを開いてしまいました。授業内容としては3人の哲学者(デカルト、マーガレット・キャベンディッシュ、ジョージ・バークリー)を中心に、私たちに見えている(もしくはそう思っている)世界の正体についての考え方の変遷を扱いました。Aレベルでも割とがっつりカバーされていた他二人に比べ、浅学ながら、キャベンディッシュについては初耳だったので、新鮮な気持ちで学んでいくことができました。
Knowledge and Reality:
こちらは認知論ずぶずぶの内容で、事前課題の本がとりわけ難しく、授業を受けてようやく著者の論を理解できる週も少なくありませんでした。レジュメたちに大いに助けられた二ヶ月半。独学の難しさ、ここにあり。セミナーで一番活発だったのもこの授業だったかもしれません。大学に入るまでは、難しい授業ほど発言が減るものでしたが、それが逆転し、いい意味での変化を感じました。来年も担当教授が一緒のPhilosophy of Languageを取る予定なので、次こそはもっとちゃんと読めるよう、励みたいと思います。
想像していた大学生活と一番違ったことといえば、春休みが明けてもTerm 3の授業はなく、代わりに試験期間になることです。正直、実際に春休みに入ってTerm 3が始まるまで私も半信半疑でした。しかし案の定、春休み期間が終わっても大学から授業の知らせが来ることはなく、試験の日になるまでぬくぬくと自分の部屋に籠る日々が続きました。そんなぬるま湯生活中に、来年からの隠居先になるであろうSenate House Libraryに出会えたことは僥倖でした。やはり、ふかふか革張りソファは正義。
学業以外ではJapan Societyの活動に力を入れた一年でもありました。そのおかげか、来年度はPresidentとして運営に深く深く関わっていくことになります。(実は、これを書いている今も、引き継ぎと9月からのイベントに向けて色々頑張っているところです。) 大きな責任を前に、少し腰が引ける気持ちもありましたが、恐れず逃れず、自分にできることをこなしていきたいです。
さて、前回は自分の輪郭がぱっきりだとかどうだとかを自分勝手に喋っておりました。今回もそのまま初志貫徹。Mobilis in Mobiliを主軸に、つらつらと、好き勝手なことを好きなように文字に落とし込んでいこうと思います。
文字に落とし込んでいく、といえば最近話題の言語化について。やたらめったら言語化するスキル〜だのなんだのがタイムラインに流れてきます。もちろん、自分の感情を言葉にすることは大事なことで、コミュニケーションを取る上でも必要不可欠です。しかしここは美術史専攻。仮にも、言葉にされない象徴について学んでいる身ですから、言語化についても何かしらあーだこーだ言えるはず。
言葉にする、という行為に対して、三年前の私はどう思っていたのでしょうか。はっきり「こうだった!」と言える何かが残っているわけではありませんが、記憶に残っている留学前の自分の発言があります。小学六年生、国語の授業でのことです。「今、私が机と呼んでいるものは、本当は椅子でも良くって。私たちがこのモノを机と呼ぼう、と。机を机たらしめているものの存在が共通で認識されているから、便宜上「机」という呼び名を使おうと言っているだけで、別にこの名称は「椅子」でも良かったんだ」― 文脈は忘れてしまいました。この考え方は、いつの頃からかは知りませんがずっと一貫して持っていて、振り返ってみると、多分どこかで唯名論(概念は名称にすぎない)にでもかぶれたんじゃないかなというような気もします。そんなことはさておき、ここで言葉にしておきたかったのは、留学前の私は、本当は、「机」と私たちが呼ぶ前の存在が何かしらあって、利便性のために、そのモノを「机」と私たちは言葉にした ―言葉は存在より下位である、という考え方。言葉にすることで、そのモノが持つ何かが失われている。そんな感覚を持っていたこと。
詰まるところ言葉を、存在を認識するための道具と捉えていたのだと思います。だからといって、私たちは言語化を通じて何かを失っている、と思い切ってしまったのは、振り返ってみれば少し極端で。例えば、感情。赤ちゃんの感情が分化していくのは、大人が赤ちゃんの感情の発露に対して名前をつけるフィードバック行為を経るから、と聞きました。他にも、色。花緑青と翡翠色と名付けられていなければ、この二つの色は同じ、緑色になっていたことでしょう。確か過去のレポート(志望理由書だったかも。Personal Statementでも使ったな)で触れたロイス・ローリーの『ギヴァー』でも、主人公は言葉を教えられる度に、モノクロの世界から溢れる色を発見していきます。言葉にしなければ元々なかったことにされていたものを、言葉にしたことで何かが失われた、と言うのはなんだかおかしな心地です。言語化によって0が1になったはずなのに、1になったことで1がマイナス(0より少ないもの)を表すようになってしまう。こう書くと、違和感がどんどん大きくなっていきます。
ここまで書いて、筆がのらなくなってきてしまいました。ので、切り口を少し変えてみることにしましょう。
みんな大好きディストピア文学。思想統制を謀る上で、言語を掌握することは常套句と言ってもいいのではないでしょうか。焚書や検閲も似たようなものではあるものの、敵性思想の広がりを防止することよりも、Sapir Whorf 仮説的な言語による思想そのもの制限について絞って話したいので、『1984年』の「ニュースピーク(新語法)」を例に挙げていこうと思います。(ここまで私に付き合ってくれている物好きな人は『時計じかけのオレンジ』の「ナッドサッド語」や『密やかな結晶』の「消滅」、『華氏451度』『図書館戦争』もこんな感じです。もし読んだことある方々いたら語りましょう。)
ジョージ・オーウェルにどっぷりと浸かる前にSapir Whorf仮説について軽く。これもまたどこかのレポートで書いたような気がしてしてならない。重複してたらごめんなさい。基本的には、話す言語によって思考や認識が変わる、という仮説です。日本語を話している人と英語を話している人は見ている世界が違うんじゃないか?とかそういう話になります。
『1984年』で登場する「ニュースピーク」は言葉をどんどん簡略化していくことで反逆的なことを思考することを、理解することを、表現することを不可能にする…という政策です。正直これが現実でも可能なら、言語は思想、あるいは現実(あるのであれば)そのもので、それこそ唯名論の世界。わくわくしちゃいます。自分的「ニュースピーク」の可能性は、前回のレポートで書いたぱっきりした自分への答えになるでしょう。同期生と英語と日本語をひっちゃかめっちゃかに混ぜながら話している時点でもう既に、私たち/私は、自分たち/自分自身に世界を少しずつ近づけ、狭めてしまっているのかもしれませんし、反対に二言語以上を扱うことで、世界を遠ざけ、広げていっているのかもしれません。(現在大絶賛フランス語勉強中なので三言語目を会得して、ベン図の中の自分の位置がはっきり見えるようになればいいなと思います。)
さて、言語化とMobilis in Mobiliに話を戻して。今の私の言葉に対する認識はどうかというと、根本的には留学前と変わりません。言葉は存在を認知し、認知したものを共有するための道具だと思っています。言葉だけでモノを表すことは不可能です。だからといって、言葉がモノの劣化コピーである……という認識は改めました。コピーではなく、クッキーの型。言葉によってモノを切り取ることで、自分の近くへ、自分の理解できる次元にモノを落とし込み、認識する。鶯色だって元は名無しのモノだったけれど、鶯色という型をつくって、そこに当てはまる部分を切り取れば、それは私たちの知る鶯色。言語によって型は各々あって、互換性のあるモデルもあれば、完全オリジナルの型もある。そして同じ言語の中でも、所属しているコミュニティによって細かく細かく型は変わっていき、その細かい変化がニュアンスや内輪ネタになる。型の数を絞って、ありきたりな四角形ばかりにすれば四角形のクッキーばかりが出来上がって、型の数を増やせば増やすほどクッキーの形は増えていく。みんなでクッキーを食べたらおいしいね。隣の芝生は青いね。そんなことを思っています。ずっと話している変化の中の変化も、クッキーの型がどんどんと増えていく中で、どれだけそれぞれの型に繊細なバリエーションをつけられるか、ということになるのかもしれません。
クッキーの例えをしたらクッキーが食べたくなってきました。クッキーの味を変えることはできるのでしょうか。型を超えて、チョコレートチップクッキーをジンジャークッキーに変えることができたら、それが世界を変えるということで、チョコレートチップクッキーのチョコチップを改良していくことができたら、それが世界を引っ張っていくということなのでしょうか。来年度は、これをテーマにできるよう、もっと広い視点を持って生きていきたいと思います。
そして、最後に、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。毎度のことですが、自分の思ったことを思ったままに広げているので、真面目に読まれるとツッコミどころが多々あるかと思います。クッキーの型論も、哲学目線で見たらまた違う結論が出るかもしれませんから。おいしいクッキーが焼けるよう、頑張ります。こんな世迷言ですら、田崎財団の皆様のお力がなければ、生まれ落ちていなかったことでしょう。ありがとうございます。残り2年間となってしまった留学生活。後悔のないよう、全力で愉しみます。
P. S. Sainsbury’sのDouble Chocolate Cookies一推しです。甘党の方は是非。
