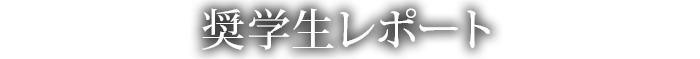
待ちわびていた大学生活も始まってみると早いもので、あっという間に1学期を終えて冬休み。2年ぶりの日本のお正月。こたつに潜ってみかんを食べる幸せを噛み締めています。
Sixth Formを離れて大学に入り、一番大きかったショックは大学での授業時間の少なさでした。1週間にレクチャー、セミナー、チュートリアル全て合わせても8時間のみ (来学期からは9時間に増えるようで楽しみです)。週に登校しなければいけない日もたったの3日。自分の自由時間が多いことに嬉しさを覚える反面、最初は生活のリズムを安定させるのに苦労しました。聞いてみると、他の人文学系の学生も似たり寄ったりな時間割だそうで、高校時代からの変化に驚きました。
授業はどれも面白いものでしたが、中でも心惹かれたのが実存主義についての単位です。実際には、「実存主義について」の授業ではなく、哲学のエッセイの書き方や考え方に慣れ親しんでいくためのモジュールなのですが、先生が美術作品や音楽、文学など、教科の壁を超えた授業をしてくださったおかげで、エッセイを書く上での小手先のテクニックばかりではなく、トピックそのものへの理解も深まりました。事前課題にカミュの異邦人やカフカの変身が登場するなど、不条理文学好きの私にとってはこの上ない天国でした。
授業外では日本人サークル、アートビジネスサークル、そして哲学と美術史のサークルに所属しています。学問系のサークルはたまにあるレクチャー以外あまり活発ではないのですが、日本人サークルではsub committee に所属したり、アートビジネスサークルと美術館へ繰り出したりして楽しんでいます。ロンドンにある美術館の数は圧倒的で、行っても行っても全く尽きる気配がありません。まだまだ巡りきれていないのですが、今のところのお気に入りは(2年前から変わらず)Tate Britainです。サージェントのLily, Lily, Carnation, Roseが展示されている時点で個人的大優勝なのですが、前学期のエッセイ課題でロスコーのUntitledを取り上げたこともあってより思い入れが深くなりました。
長いようで短かった1学期、振り返ってみるとCH時代よりも自分の輪郭がぱっきりしていたように感じます。新しい環境に入り、新しい人間関係、新しい自分を心がけた、というのもあるかもしれません。しかしこの冬、旧友と話している中で「英語の私」と「日本語の私」のじんわりとした融合も一因なのかな、と感じました。何がきっかけでそう思ったのか、どう言語化したらいいのか、そもそもなぜこのレポートにこの一文を載せようと思ったのか、なんともまとまらないのですが、備忘録も兼ねて少し書いてみたいなと思います。
そもそも自分の輪郭がぱっきりってどんな感覚なのでしょう。日記にそう残しているからには、2ヶ月前の私には完全に意味の通る言葉だったのでしょうが、擬態語の瞬間性を時間が経ってから再現するのは自分でもなかなか難しいようで。ひとつ思い当たるとするなら、人間として自分の歩いていきたい道が少しずつ見えてきたことでしょうか。ずっと水のようでありたいと思っていた自身に片栗粉を突っ込んでバシャバシャしてみたい欲が生まれました。今でも常に流れていたいとは思うものの、たまには激しく自分の主観を持てる人間になりたいな、と。それとも、もしかしたら、ぱっきりはもう何も関係なくて、ただ単に語感のいい言葉を並べただけなのかもしれません。正直、よくやってしまうので。2ヶ月前の自分に空回りさせられるのはなかなか悔しい気持ちもありますが、相手は自分自身なのだからしょうがないと言い聞かせるしかありません。
そんなことはさておいて、最初に渡英してから2回の帰国を終え、やはり感じるのは使う言語によって自分の言葉の選び方や性格が変わるな、ということです。特に同期生と話していると顕著で、「あれ私こんな言葉の使い方する人だったっけ」と我に帰る瞬間が度々あります。もう元々の言葉遣いを覚えているのかも怪しいのですが、つい昨夏に帰国した時は周囲から「変わらないね」と言われたのに、今回の帰国では「あ、変わったな」と自覚する場面が多く、これは成長?退化?歪み?洗練?―戸惑いました。いくら新しい出会いが多かったといって、2年間で変わらないと言われたものが3ヶ月で変わったとは思いません。積み重なってきていたものが一気に起爆されたのか、19歳になってようやく少しは成長したのか、それとももう考えなくなってしまったのか。色々と言葉を転がしてみて一番しっくりきたのは「私が私にまとまってきた」。きっとこれもぱっきりと同じように薄れていってしまうのでしょう。そんなことも受け入れて、取り戻して、信じて、進んで、自分の大学生活を最大限に味わい尽くせるよう、残りの半分も過ごしていきたいと思います。
