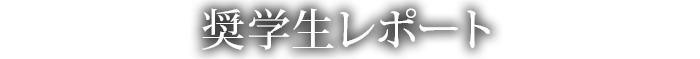
同じ地で過ごす三度目の冬となり寒さにも慣れつつあることにすこし特別感を感じています。紆余曲折はあったものの僕の好きな街で、好きな建物を眺めながら、それでも全くの新環境で好きなことを勉強できるようになったことをうれしく思っております。
今までFettesにいたころはあまり好きなことの勉強に熱中できることはありませんでした。建築に関しては本を読んだり、ポッドキャストを聞いたり、絵を描いたりというほうに重きを置いてしまい、主体的なアプローチになっていたかと問われると首をかしげてしまうような学びだったかもしれません。しかし大学に入学し、建築というものに学問およびトレーニングとしての学びをするようになりとても学習面への満足度が上がったと思います。建築史のコースでは大量の文献を読み漁りノートを作ったり、エッセイを書いたり、コーヒーとクッキーを目の片隅に友達と夜遅くまで図書館にこもったりなど一つのコースなのにそれだけで忙しくて思い出を作れるような日々を過ごしました。その対価として得た知識は散歩しているときに隣にいる誰かに語ってしまうという二次災害を引き起こしています(この被害を受けた方々申し訳ございません、多分これからも続きますがご辛抱ください)。もともと人文サイドの建築に興味があり選んだ大学であったので、その志望に沿う学びができていることに心から嬉しく思っています。次の学期でも現代建築のコースがあるのでそれもとても楽しみにしております。
他の二つのコースはアートがベースのコースでした。チュートリアルとデモとプレゼンと創作のセットが一週間中に起こるこのコース二つのせいで寝れぬ日が続くこともありました。創作活動はすべて建築学部の専用スタジオでやっていたため、学期中スタジオに行かない日はほぼなかったほどです。しかし、そのおかげか制作に対する意識は確実に上がり、スキルも速度もプレゼン力もついてきたように思います。やっていることはとても面白く、教授のフィードバックも興味深いアドバイスばかりで、身体的には疲れるタームでしたが制作中は頭の中で楽しいBGMが流れていました。大学になっても努力に比例しない主観的な成績評価になっていますが、結果は後からついてくると信じて頑張ります。
生活面に入って、大学だと社交的になろうとすると自分がエフォートをいれて行動しなければいけないというのがおそらく一番のFettesとの違いで苦労したところだと思います。大学には日本でいうサークルであるソサエティやクラブが数え切れないほどあります。しかしそれらに参加したり、寮のフラットメイトだったり友達の友達からじゃないとなかなか人脈が広がっていきません。Fettesのころは所属していた寮だったりクラスが同じ人などと友達になっていったので今考えればシンプルだったなと感じます。
交友関係を広げていくにあたって気づいたことがあります。これはもしかすると僕の周りだけなのかもしれませんので一般化するのは難しいですが、大学にいる人たちは割と裕福だと感じます。一見当たり前のように思える主張ですが感じることがよくあります。前提としてインターナショナルの生徒は概ね皆裕福であることは簡単に納得できます。学費はHome Studentの約4倍であり、かなり裕福でないと生活費も含めて出せないものです。政府や学校が出している奨学金があるとはいえ大半の生徒は富裕層に属していると思います。しかし、Home Student、そして少し意外なことにスコットランドの生徒もお金持ちであるということです。スコットランドの大学はスコットランド市民には大学学部無償にしています。そのため、僕は勝手にもスコットランド市民枠で入学している人たちは皆が裕福なわけではないだろうと考えていました。しかし周りにいるスコットランド人含めたイギリス人は皆上級アクセントで富を感じるバックグラウンドをさらりと話して来ます。スコットランド人の友達と話していたところ、イギリス全般で言えることかはわかりませんが、街ごとの経済レベルがあるそうです。そうすると必然的にお金持ちが住む街の学校が富裕層の子どもといい先生がつどい、となってしまうそうです。それに対する施策として富裕層でない地域の学校には大学に必要な成績のハードルを下げるなどということを行なっているそうですが、それは大学につきに限られた人数にしか行われないようです。こうしておそらく比較的いい大学には金銭に余裕のある生徒が集まっていくのだと思います。
これを考えた時に経済格差が与える教育格差というのは決して決まった一つに起因するわけでないんだなと思います。学歴社会が根を張る日本では、いい大学に入るためには高校教育だけでは難しく、高いお金を払って予備校に行くことが一般とされて来ています。私立の学校に行かせることも私立大学というのも経済レベルが物語る教育の差であると思います。しかし日本ではイギリスと違い、経済が教育に直結します。イギリスではそこに階級という乗り換えがあります。予備校などには通わせることは不必要だとしても、その地域中学校高校によって差が出てくるシステムなのかもしれません。それを改善する策が施されているという点ではイギリスの方が一時的解決を促しやすいと思います(名門大学に入るのは金銭はどうしてもかかってしまい、それに対する解決策はなかなか難しいものです)。
日本の高校の時の研究の際に算出した結果、日本における経済レベルと教育のレベルの相関指数は0.8を超えていたのを覚えています。解決策が見出しにくい日本の教育システムはなかなかに恐ろしいものだと思います。しかし階級という問題が絡むイギリスのシステムも、階級に縛られるという面で怖いものだと思います。
少しネガティブめな文化考察が長くなりましたが、大学は忙しくしながらも楽しめております。そして今回の考察トピックを半ば第三者目線で考えられている自分の状況に、財団には心から感謝しています。今後とも自分の好きな学問の学びを広げ、将来の専門へのトレーニングに邁進していきますので、よろしくお願いします。
