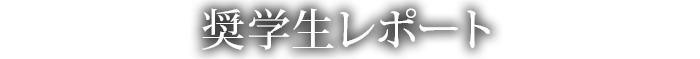
題:「カフカ」と「ガリレオ」と「ニュートン」
ロンドン中心部、シャーロック・ホームズの住むベーカー・ストリートからリージェンツ・パークに沿って北へ15分程のところに、”カフカ“と”ガリレオ“がいる。
ここでいうカフカとは、チェコの小説家、ではなく、
ここでいうガリレオとは、イタリアの学者、ではなく、
村上春樹の『海辺のカフカ』と、東野圭吾の『探偵ガリレオ』に始まる連作ミステリーシリーズ『ガリレオシリーズ』の”ガリレオ”である。
St. John’s Wood LibraryというCity of Westminsterが運営する公立図書館に、日本の蔵書があると知ったのは今年二月で、久しぶりに日本の小説を読みたいと思ったものの、時間が見つからず、なかなか訪れられずにいた。
また一年が過ぎ、ロンドンでの大学生活も半分終わってしまったが、化学をより広く深く知り、理解し、勉学に励み、充実した日々を過ごし、昨年度に引き続き今年もDean’s List (成績上位10%の者に与えられる) に名を連ねた。
この夏は、日本に帰らずにImperial College London (以下、ICL)の化学科・化学工学科・機械工学科など複数の学科と他大学を跨いで組織された「多層プラスチック (MLP) のリサイクル」をテーマとする研究チームに属し、研究に没頭する日々を送っていた。私はそこで、新しい化学的なリサイクル方法を確立するためのデータ収集と分析、プロセスの物理化学モデルの構築、システム全体の最適化などに取り組んだ。
この夏、日本に帰らず、このまま日本の小説が読めず仕舞いか、と思っていたところで、件の図書館の存在を思い出したのである。
下手をすると、学期中よりも化学にかけた時間が多かったかもしれない夏休みの中で、時間を見つけ、ようやく訪れることができた。図書館自体はそこまで大きくないにも関わらず、日本の小説・随筆など幅広く相当数蔵書しており、ありがたい限りであった。
そういう訳で、この夏、”カフカ”と”ガリレオ“を読む機会を得たのである。
”カフカ”と”ガリレオ“とニュートンが、この夏ICLで研究を経験した私にどのような影響を与え、何を考えさせ、どのような道標を与えたのか。そして過去二年間の学びを振り返り、この先の二年間を臨むとき、何を思うのか、それらについてまとめることがこのレポートの大枠である。
さて、『海辺のカフカ』をまだ読んでいない方にはぜひ手に取っていただきたい。既に読んだ方は共感してくださるかもしれないが、読み終わったときの私の率直な感想は、「今まで出会ったことのない小説」だった。文章は大変読みやすいのに、展開や世界観は現実離れして複雑で、それでいて不思議と納得してしまう。しかし心には何かが引っかかり、形容し難い余韻が残る。そういう不思議な印象を与える小説だった。もう少し深く考えたくなるポイントが随所にある。
結局、村上春樹はこの作品で何を伝えたかったのか。
考えられるテーマは多く、どれも適当ではあるけれど、いずれも最適解ではない。
この作品についてあれこれと思考を巡らせていたところ、もしかすると、この永遠にすっきりとしない思考こそが、作者の狙いだったのかもしれない、と思い始めた。村上春樹はこの作品に無数の「思考の沼」とも呼べるトラップを仕掛け、読者に考え続けさせようとしたのかもしれない。
学ぶこと・考えることを止めてしまったとき、それはその世界を自らの手で閉じてしまうことを意味する。逆に学び続ければ世界は広がり、考え続ければ世界は深まり、世界の解像度は高まって行く。考えることを止める、というのは本来無限に広がる可能性を秘めたその世界を自らの手で閉ざしてしまうことに他ならず、極めて罪なことなのかもしれない。
この視点から見ると、『海辺のカフカ』と化学が重なって行く。
この夏に経験した研究は、学期中の学生実験とは大きく異なる。学生実験が「既に立証されたことを追体験すること、答えを確かめること」だとすれば、研究は「新しい答えを見つけ出すこと」と言えるかもしれない。私が得た実験データ、考察、結論が果たして正しいのか間違っているのか、誰にもわからない。だからこそ、自分の研究データと考察に責任を持たなくてはならないのだが。
ここで登場するのがニュートンである。
イギリスの科学者、アイザック・ニュートンはあまりにも多すぎる偉業を成し遂げ、現代に通ずる自然科学の大枠を作り上げた”巨人”なのだが、そのニュートンがロバート・フックに宛てた書簡に、「巨人の肩の上」という有名な一節がある。自然科学というのは、過去に積み上げられた無数の偉大な発見や理論の上に組み上がっていくものである、という意味の言葉だ。ニュートンは、先代までに組み上がった巨人、の上に立った巨人だった。
学期中、講義で理論などを学ぶことは巨人のつま先から肩を知ることであり、実験を通して知識を実践的に使い、巨人の理解を深め、考える練習をする。一方、研究は巨人という過去の知見や理論体系と整合性を保ちながら、より説得力のある結論を導くこと、と言えるのではないだろうか。そして研究には区切りはあっても終わりがない。
学生実験には、時間も物資も提出するレポートの字数にも制限があり、どこかで「考えるのを止める」必要がある。もちろんその限られた時間の中でどこまで考えられるか、という点もスキルとして大変重要なことなのだが。一方、今回の研究ではそのような制約が少なく、心ゆくまで実験し、実験データを多角的に観察し、あらゆる可能性を一つ一つ丁寧に納得できるまで考察する、という経験ができた。巨人の肩の上で今の私にできる最大限の背伸びを試みた。もちろん研究の道は険しいこと間違いないだろうが、化学について考えることが何よりも楽しかったこの夏の経験から、飽くなき探究心と達成感がその険しさを凌駕するだろう、と思う。将来も化学と共にありたい、との思いをより強くした一年だった。
『海辺のカフカ』を通して学んだ「考える」ことの大切さは、当然化学に限った話ではない。作中に登場する戦争や学生運動は、争いごとの象徴として描写されているようにも感じるが、争いは異なる正義の対立とも言える。その正義どちらが正しいかは関係なく、互いに相手の正義への想像力を働かせるのを怠り、相手の立場について考えることを怠ってしまったとき、武力行使しか道が残っていないのかもしれない。過去4年間イギリスで過ごし、多様なバックグラウンドを持つ人々と関わりを持ったことは、間違いなく自身の世界を広げ、自身の想像力を大きく広げたと思う。
真剣に考えることは大変エネルギーを要することでとても疲れることだが、世界を広く深く生きていくためには、やはり考え続けなければなるまい。このとき、『海辺のカフカ』の主人公がなぜ「世界で一番タフな15歳にならなくちゃいけない」のか、なんとなく分かった。
「ガリレオシリーズ」も大変面白い作品で、”ガリレオ先生“こと物理学者・湯川学は節々で考えることの大切さを説いており、”カフカ”に通ずるところも多い。だがそれに留まらず、湯川学の研究・実験に対する姿勢が、この2年間で出会った教授方、この夏に私の研究を共に進めてくださったポスドクの研究姿勢と重なるところがあり、非常に重要なことをたくさん学んだ。ここではそのうちの3つを紹介したい。
まず一つ目は、何事も実験してみる、ということ。結果が大方予想つくような非常に簡単なことでも、手を動かして実験して確かめてみた方が良い。おそらくこうなる、どうせこうなる、と高をくくることは研究者としてあるまじき態度であり、そういう場合は特に、実験してみた方が良い。例え、結果が予想通りであったとしても、その過程を観察することで新たなアイデアを得たり、理解が深まったりするからだ。
二つ目に、実験に失敗というものは存在しないこと。実験は仮説を立証するために行う訳だが、例えその仮説に反する結果が得られたとしても、それはその仮説ではうまくいかないことが示せたという点で、非常に有意義である。
三つ目は、思い込みやバイアスを限りなくゼロにすることである。湯川学も「思い込みはいつだって敵だ」と述べたように、思い込むことで見えるはずのものも見えなくなってしまい、考えを歪めてしまう。振り返ってみれば、仮説がいつの間にか正しいと思い込んでしまっていたことが何度かあった。仮説に基づいて実験や考察を繰り返すうちに、その仮説が自己暗示のように刷り込まれて行き、いつの間にかその仮説が正しいことのように思い込んでしまっているのだ。そういうときは当然考察がうまくいかなくて苦しむ。そしてふと我に返って自身を客観視できたとき、思い込みが除去され、より明瞭な考察が可能になった。人は思い込みの生き物だろうから、意識的に思い込み・バイアスを解除しなければならないことを実感した。
茫漠たる化学の海を前にすれば、私がこの2年間で学んだことなど微々たるもので、危うく絶望しかけるが、振り返れば確かに成長してきた訳で、これからも漸進すべく精を出したいと思う。
さて、このレポートを書いたのはICL 分子科学研究所の一角である。ちょうど背後で進行中の実験が終わりそうなので、ここで筆を置くことにする。
このレポートを書くにあたって大変参考となる議論を展開してくださった、同期のK. B. (Durham University, Mathematics) に深い敬意と感謝を表する。
最後までお読みいただきありがとうございました。
