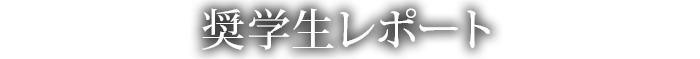
大学一年目が幕を閉じた。一年目を終えるに際し、「大学生活はどうだったか」とよく聞かれる。思い描いた通りの大学生活だった、とは言いきれないが、実際にさまざまな難しさはあったものの総じて充実していたことには変わりなく、高校までとはまるで異なる学校生活であったことに刺激を受けた一年であった。今回のレポートでは、前回のレポートと重なる点もあるが、私の実感として高校までの学校生活や学習とどのように異なっていたのかに再度焦点を当ててまとめたいと思う。
まずは大学生活の要、勉強についてである。基本的には自分主体である点は大きく変わらないが、高校時と比べて自由度が高いため、自己マネジメントの重要性が増したように感じる。一日や一週間のスケジュール内で授業のコマ数が少ないこともあるが、長期的に見ても空き時間が多い。二学期制のアカデミックイヤーのうち、二学期は四月頭に授業が終了し、イースター休みの後はテストを経てすぐに夏休みに入る。すなわち、早い人では四月下旬から、遅い人でも五月下旬には一年間の全課程が終了するのである。今年の私のテストは試験が設定されうる最後の日程に行われたが、それでも5月23日には第一学年が終了した。その一方で先学期と変わらず、授業期間終了前などはかなり忙殺される時期である。エッセイ等の課題の締切、試験勉強に加えて通常の予習・復習が重なる。授業の予習・復習といっても言語系の授業を多く取っていた私にとって、授業内容を復習し、毎日30〜50行のラテン語や古代ギリシャ語を分析して理解したのちに英語に翻訳する予習を週3回から4回行うことは慣れても簡単なことではなく、到底日々の時間では足りなかった。しかし、このように時間とやりたいこととの板挟みになりながらも、計画性を持って取り組めたのには、大学入学前2年間のオンラインスクールでの経験が大きいと感じた。Aレベルを受けるまでの間、学校の時間割に縛られない代わりに自由時間が多かったため、どのように時間を活用するかを培ってきたつもりであった。その功為して、自由時間が多く、制約の少ない大学生活においてもやるべきことを見失わずに計画性を維持できた点では良かった。
さらに、大学に入って大きく変化した点の一つとして、勉強の方向性が挙げられる。高校生まではどうしても目前の試験に向けた勉強に集中しがちである。例えば、授業で分からない点があって先生に質問しても、高校のテスト範囲ではないから、ということで曖昧な回答をされた経験が一度や二度ではなかったことを記憶している。前回のエッセイでも触れた通りであるが、エッセイ課題についてはどのようなポイントを押さえていれば何点がもらえるというように点数が判断されることが多かった。実際に2023年に出題されたラテン語のエッセイ課題の一つに「(課題の文学作品において)どのようにその作品が読者を惹きつけているのか」という問題がある。この問いに答えるには、修辞法やその作品の背景知識を幾つか暗記して引用し、それを問題の答えに沿うように考察してまとめるというのが定型である。この類の抽象的な問題がAレベル試験の点数配分としては最大になるのだが、これらの問題は練習を重ねていけば重要な箇所を対策することは難しくないはずなのである。
一方で大学のエッセイは高校までのそれとはかなり違う。第一に他の研究者の論文を読み、それを元に自分の考えなり新たな持論を述べる必要がある。まさに「巨人の肩の上に立つ」ことがベースとなっている。第二にそのような根拠を明確にし、順序立ててわかりやすくまとめることが重要視されるため、どのポイントを書けば何点、ということは明確になっていない。それどころか、模範回答たるものが存在するかも分からない。言い換えれば、エッセイの採点は担当した教授の主観によって変わり得るということである。そのため、大学ではエッセイに慣れるためにさまざまなサポートがあったことは大いに助かった。例えば、提出前の課題にライティングセンターというものがある。採点担当ではない教授に第三者の目から添削とアドバイスをいただける機関であり、自分ではしっかりまとめられたと思ったエッセイでも他者の視点を通すことで、初めて読む人に対してどこが不明瞭かがわかるようになる。また、採点者からのコメントもかなり鋭いものであり、それでも分からない点については先生方から直接詳しい説明をいただけることもあり、次回への改善点としてとても役に立っている。実際に一学期では高校と大学のエッセイの書き方の違いという壁を前にかなり苦労した点数も、二学期には回数を重ねるごとに点数が伸び、最後のエッセイでは一年生が到達できる最高点、75点のうち72点をいただくことができた。もちろんまだ大学の一年目であり、大学での学びを語れるほどのレベルに達したわけではないが、その入り口に立っただけでも高校までの暗記や定型文が通用しないという、別次元の世界に来た気分であった。
学業は大学生活の軸であるが、その一方で学業だけに固執し続けることはできない。イギリスでの高校時代には、それによって精神的な逃げ場を失い、ストレスを溜めた末に自分を追い込んでしまった経験もある。そのため、大学では学業とのバランスを取るためにもクラブ活動やソサエティに参加することにしていた。特に幼い頃からバレエを続けてきたので、前回のレポートでも触れたように大学ではダンス部に所属してバレエを踊っている。今学期はコンペティションや舞台が多かったことから先学期以上に忙しさを増したが、2月から3月にかけてはエジンバラ、ニューキャッスル、スターリング各大学のダンスコンペティションに参加し、私の所属していたクラシックバレエ上級者のチームではそれぞれ3位、3位、1位を受賞した。10人のチームワークであるため、大会や舞台ごとにチーム仲が深まり、それ故に勝利した時の喜びは並大抵ではなかった。しかし部活では舞台に向けた振り付けとリハーサルが主になるため、思うようにバレエを踊ることはできない。そのため、地域のバレエ教室でレッスンを受け、基礎としてのバレエ自体の練習も続けることができた。
また、文化部系としては友人の勧めでICE (International Café of Edinburgh)という、キリスト教の慈善活動をもとにしたコミュニティに参加していた。このソサエティでは毎週水曜日に各国出身の学生がそれぞれの国の伝統料理を振る舞うというもので、週替わりで様々な国・地域の食事を無料で振る舞っている。私もJapanese nightの際に数名の友人や知り合いを集って巻き寿司や焼き餃子などを作った。少人数で限られた時間内に約80人分調理しなければいけないため、かなり大変ではあったものの、日本に関心のある人も多くとても好評だったのでやりがいを感じた。また、このような集まりで参加者と話すうちに自分の興味関心と近い新たな友人の輪も広がった。大学生活では高校までの閉鎖的な環境とは異なり、開放的な空間に立たされることになるので、自発的にコミュニティに参加していかないと友人と出会うきっかけを逃してしまいやすい。このような集まりで参加者と話すうちに自然と自分の興味関心と近い新たな友人の輪も広がったことにもソサエティの重要性を実感した。
大学一年目は学習面においても生活面においても高校までとの違いに順応していくことが最優先であった。一年が巡り、こうして改めて振り返ってみると、新しい環境で再スタートできたことで高校までの反省を活かしつつ、学習面でも生活面でも充実した一年間であったことをしみじみと実感する。九月からの新学期では二年生として新たな一年が始まる。大学生活に慣れて余裕が生まれることで視野が広がり、より充実した大学生活になることと思う。その中でも自分の軸を見失わずにいただいた環境を満喫したいと願う。
