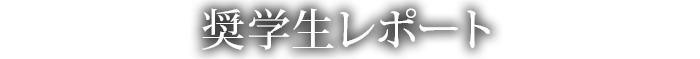
4年という月日には、一体どれほどの重みがあるのでしょうか。
世間一般では4年と言えばフィールズ賞の発表が再び訪れ、応援しているフットボールチームの選手はあらかた入れ替わり、新年にバグパイプで 'Auld Lang Syne' を演奏するのも数えること4回目となるような長さの時間ですが、そうした形而下的な一面を離れて個人の内面に潜り込んでみると時の蓄積というのはより一層強烈に襲ってきます。
この4年間で僕自身に起きた変化として一番大きなものはもちろん将来の進路の変更です。元々地理学部志望でいつかは都市計画に携わりたいと言っていた人間が、いつの間にか生粋の数学屋になってアカデミアを目指しているというのは自分で何度考えても不思議なことです。それもまた時と環境の変化が成せる業なのでしょう。そして学業以外の個人的/性格的な部分を取っても、4年前に日本を発った自分と現在の自分の間には一目では分からない、けれど確かにそこに横たわっている違いというものが感じられます。
何故こんなことを急にしみじみ考え始めたかと言うと、このレポートを書くにあたっての自分の姿勢の変化に驚かされたからです。留学初期の自分にとって、ものを書くというのはとにかく自分の思いの丈をぶつける手段の一つであったように思います。もちろん事実に反することや極端に偏った意見が見て取れてしまうような文章にならないように注意を払ってはいましたし、自分の述べたことほぼすべてはきちんとした裏付けや推論に基づいているつもりです。しかし、その論の根底には必ず出発点となる自分の主張/信念が存在していて、文章(レポート)を書くことはあくまでその主張を正当化し第三者に伝播させるための道具に過ぎないという側面があったことは否めません。つまり始めから終着点は決まっていたとも言えます。こう書くと少しネガティヴに聞こえてしまうかもしれませんが、決してそれが悪いことだとかそうすべきではなかったと言いたいのではなくここでは自分の文章を書くことへのモチベーションは「自分の思うところを他者に対して主張する」ことにあったと整理しているだけです。
ところが翻って今現在のモチベーションがどこにあるかと問われると、どうもこうした以前まで抱いていた気持ちとは少し違うようなのです。上手く表現するのは難しいですが、何かを強く訴えたいという思いが自分の中から消えているといつからか気付いてしまいました。何故そんな現象が起きているのか、思い当たる節は幾つかあります。一つ、主用言語の変化。一つ、専門分野の変化。そして最後に、世界観の変化です。綺麗に纏めたかったのでそれらしき単語を並べてみましたが、実際にそれぞれがどういう意味なのか深掘りしてみましょう。
1. 主用言語の変化
まずは主用言語の変化についてです。過去にも触れたように(また留学中の同志の皆様が日々感じておられるように)、日本語を第一言語として育った身からすると英語を日常言語として扱うのは一苦労です。そもそもの文型の違いに始まり、ネイティヴの言い回しに、スラングにそしてアクセントに翻弄される毎日が続きます。とはいえそうした実用的な問題にはとうの昔に慣れ、文中の単語一つが分からなかったり新種の訛りに出くわして戸惑ったりすることは未だにあるにせよ「英語を使う」という壁は大方乗り越えたと言っていいでしょう。
その一方で、言語とは思考の顕在化という一面も持っています。自分の頭の中に無いことは当然発話することもできないのです。対偶を取るとこれはすなわち「発話している内容はすべて自身の頭の中に存在している」ということになります。つまり英語で新しい表現を学んで使う度に、或いは以前まで英語でできなかった会話ができるようになった時に、我々は自分の中の思考の領域がまた拡がったことに気が付くのです。拡がると書きましたが、僕の中の感覚としてはシフトすると言った方が近いかもしれません。悲しいことに人間の脳のキャパシティは有限なので、処理すべき情報が一箇所に集中するとそれ以外の部分の管理は疎かになってしまいます。よって新しく入ってきたものは元々あったものを自然と押しのける形でそこに存在するのだと思います。
自分の思考回路に起きているのはまさにこのシフトなのかもしれない、とはごく最近自覚し始めたところです。去年のレポートで「周りの人たちとの共通認識が養われてきた」と述べましたが、これは主に思考が新しい方向に「拡がる」方に重点を置いた議論でした。そこで留まっていたのは恐らくこの時はまだ何かを失っている感覚を持っていなかったからでしょう。その先の気付きに進むきっかけは何だったかというと、去年に引き続きサポーターとして参加させて頂いた8月のTOPSだったと思います。そこで出会った財団の先輩・後輩や高校生たちと様々な会話を重ねる中で、久しぶりに日本語 - 日本での思考回路、と言い換えましょうか - を使う感覚が蘇ってきました。もちろんそれまでも英語で話す自分と日本語で話す自分が若干異なることには気付いていましたが、その違いや日本語の揺れを今回ほどはっきり突き付けられたことは過去に無かったので少し驚きました。具体的な事例を挙げるならば、一人称がおぼつかなかったり(「僕」と「私」の両方を混ぜて使うようになってました)語彙が変になっていたり(類語検索したり英語→日本語で訳さないと思い出せない単語もありました)でしょうか。また、そうした変化を認識すると同時に痛感したのは日本語側の性格でいることの容易さです。「素を出している」と表現すると「本来の」性格という不本意なニュアンスが出てしまうので、「長く慣れ親しんだ方の」性格が出ていたと言えば一番正しいでしょうか。如何に表向きの生活に慣れてどれだけイギリスに染まった気になっていても、内面が - 生まれてから17年積み上げてきた - 日本での性格と肩を並べるくらいに馴染むにはまだまだ時間がかかるのだと実感しました。
この言語環境による性格の切り替わりは、例えるならば車の車線変更のようなものです。僕の中には日本で培った性格とこちらに来てから育った性格の二車線が存在し、僕はその間を行ったり来たりしているのだと思います。この例えに従うと、上述の現象の多くにもちょうど当て嵌まる説明がつけられます。思考が拡がるとは新しい車線をつくる過程のこと、TOPSで自分の変化に驚いたのは英語から日本語に戻る時にその車線間の距離が以前より開いたことにふと気付いたから、そして未だに日本の性格の方がよく馴染むのはイギリス側の車線がまだ整備されきっていないから。似たような例えは誰についても言えるのではないでしょうか。ある人は性格の違いを感じることはあれどそこまで明確に分かれていないかもしれないし(車線間の距離が近い)、ある人は切り替えが意のままだったりするのでしょう(これは道というより車の性能の違いでしょうか)。または複数の性格が上手く両立されていること(車2台持ちパターン)やそもそも性格の違いなんて無い場合(一車線パターン)も考えられます。性格なんていうあやふやなものはそれこそ人の数だけ解釈の仕方があると思うので、是非とも複数言語話者の皆様にはその感覚を言語化して共有して頂きたいものです。
では具体的に何が英語圏に来て変わったのかと問われるとまた難しいですが、自分でもすぐに気付く点を挙げるならばコメントの主体性とインプットの量・質の二つです。前者については、会話の中でのボケの数とでも言いましょうか。日本語で話している時は自分の方からその先のやり取りの導線になるようなことを言う機会が多いのですが、英語では会話を一区切りさせるようなコメントをする方が比較的多いです。もちろん英語でも話題は振るし日本語でもツッコミに回ることは全然あっても、傾向として日本語では一言投げて誰かの呼応を待つのに対して英語では誰かの発言を受けてそれに応える形が主だと自分では分析しています。後者について言うと、圧倒的に英語でのインプットが足りていません。僕は日本では多読家でしたがやはり英語で同じことをするのは依然難易度が高く、読める冊数は限られています。代わりに会話や諸メディアを通して耳から入れる情報は増えている気はしますが、そこから受け取れるものは偏るし限定的です(余談ですが、このインプットの性質の違いに表意文字である日本語と表音文字のアルファベットそれぞれの強みが反映されている気がして面白いです)。
ここで元の論点に立ち返ると、自己主張の意思が弱くなった理由の一つはどうやらこの言語シフトによる性格の切り替わりだと考えられます。誰かの発言を受けてから話すことが増えたが故に自分が思ったことをまず発信したいという意識が下向いている、とはそれほど飛躍していない論理でしょう。そして良いものを書くために良いインプットは不可欠ですから、読書量の変化に代表されるインプットの減少がそれに輪をかけているのは間違いありません。こうした要素が重なって書きたい/伝えたい意欲の低下に繋がっているのだと思います。
2. 専門分野の変化
さて、次に専門分野の変化について考えてみます。振り返ってみると、地理/都市計画志望だった頃(留学後1年くらいまで)はやはり社会構造一般について考えたりそれに関連するテーマで文章を書くことが多かったです。A-levelの地理の授業では国家間の経済発展の違いや都市内での環境格差などを大きな単元として扱っていましたし、併せて取っていた経済でもマクロ経済の概論といった高い視点を持つことを意識する内容になっていました。もちろん課外でも地理学部を目指すからにはその方面の造詣と実績を積む必要もあったので、エッセイをコンペティションに出したりオンラインで記事やサイトを漁ったりと本当に色々なものに触れていたと思います(前段の論を用いると「良いインプット」が多かった訳です)。そしてそこに個人的な背景 - 昔から日本の学校教育等について思うところがたくさんあったこと、そしていきなりイギリスのパブリックスクールへやってきてカルチャーショックを受けたこと - も重なって、当時の僕の頭の中は叫びたい気持ちでいっぱいだったのでしょう。渡英後6カ月・9カ月のレポートを読み返すとその傾向が如実に見て取れます。さらに6カ月レポートに対する自己反論なるものも(公開こそしていませんが)その間に書いていたりと相当自分の考えを文章に起こすという作業に力を入れていたことが分かります。
その意識は明らかに数学科に転向して変わりました。数学をするとなると人文系の話題に触れる機会が減るのは当たり前と言えば当たり前のことなのですが、その自明な理由以外にも幾つか触れておきたい要素があります。まず、数学とは(聞こえの良い表現を使うと)ひたすら自分の理解力と向き合う学問であるということです。よくある誤解として数学科は小難しい計算テクニックを学んだりより早く計算ができるようになるための場所だというものがあります。確かにそういった技術もきちんと勉強していれば向上しますが、それはあくまで副産物に過ぎません。数学科の時間の99%は定義を覚え、定理を理解しそしてその証明を読んでなぞることに充てられます。要するに読解です。何故そんなことをするかというと、大学以降の数学の目的はすべてを一切の矛盾なく厳密に構築することにあるからです。その過程で、ある主張が正しいか正しくないかを判断する材料は証明しかありません。もし与えられた前提と矛盾ない推論から得られた結論ならばそれは真だし、逆にどれだけ正しく見えても証明が出来上がるまでそれは真と認められないのです。そんなデリケートな対象を学ぶ上で重要なのが「自分はこれを本当に理解しているのか」と常に確認することです。定理をサラッと読んで分かった気になるのは簡単ですが、そこに登場する定義すべてを諳んじることができるか、書かれている証明の行間(飛ばされたステップ)を自力で埋めることができるか、数日後に見返して証明の流れをきちんと覚えているかと問い続けていくと相当な読み込みと記憶が必要になります。一つの証明、高々数ページに丸一日かけるのも珍しくはありません。
こうした作業を繰り返すと辿り着く境地が極端なまでの内向性です。どこが理解できてどこでつまづくかは人それぞれなので、複数人で同じ内容を勉強していたとて互いに助け舟を出すことはできても最終的には自分が理解できるかできないかのみが焦点になります。さらに他の多くの分野 - 特に人文系 - では理解するというフェーズの後にエッセイやディスカッション、或いは実験といったアウトプットの機会が存在すると思いますが、我々数学徒にはそんな贅沢もほとんどありません。数学科の学部生としてのゴールはひと通りの数学の基本的概念を理解することに留まる(一人前に研究ができるようになるのはまだまだ先のことです)ので、何かを生み出す方に関わるというのは稀です。そんな自己完結的性質のおかげで、数学にのめり込むのに比例して自分の外より内に目を向ける時間の方が圧倒的に長くなるのは自然なことと言えます。
そして、その一般論に拍車をかけているのが僕の個人的な事情です。最近の悩みとでも言いましょうか、目下のところ身の回りに同じレベル・同じ熱量で数学について語れる人間がいないのです。ダラムの数学科はもちろんそれなりのレベルであるはずですが、未だに同志と呼べるほどの数学への入れ込み方をしている人に出会えていません。成績が僕より上の人間も何人かはいるのですが別に名前が公表される訳でもないので誰だか分からないし、教授に話を聞きに行けばもちろん説明はしてくれても彼らはまた住んでいる世界が違うのでちょっと話し相手に…という訳にはいきません。そんな訳で本を読み進めたり授業では扱わない分野に首を突っ込むといった活動は結局一人でこなしています。まあそれはそれで楽しいし別にいいのですが、「周りにこの話ができる人がいればいいな」と思うことはよくあるのでそろそろ学外やオンラインに捜索の手を伸ばしてみるべきなのかもしれません。
まとめると、数学科の性質に加えてこうした現状もエネルギーを内側に向ける原因の一つになっていると思います。アカデミアの良いところの一つは勉強や研究が自分主体で進められるという点ですが、今の自分は逆に周りとの繋がりが無さすぎる気もするので(元々の性格に起因するところもあるかもしれませんが)それがアウトプット意欲の少なさを助長しているのでしょう。
3. 世界観の変化
それでは最後に「世界観の変化」について見てみます。導入部では一単語で上手く表現したかったので世界観という曖昧なワードを持ってきましたが、それの意味するところを書き出すと「社会の中での自分という存在についての認識」となります。正直この点に関しては自分でもあまり深く考え抜けていません。なので本当に取り留めのない段落になると思いますが、良ければお付き合いください。
まず4年前と現在の間にある違いを端的に記述すると、以前は自分が動けば社会の何かが変わると信じていたのに対して今はその確信が持てない/むしろ変えられないと思ってしまっている節がある、となります。こう書くと何とも志低いネガティヴな人間に成り下がったなという誹りを受けてしまいそうですが、これですべてを説明しきれている訳でもないのでジャッジするのはまだ早計です。
4年前の自分がどういう考えを持っていたのかというと、ある種の全能感だったのではないかと今になって思います。ちょうど留学の入り口に立ち、そこからどんな可能性も開いている状態。そして新しい環境/人/情報に触れて頭の中が整理されきっていない状態。(過去何度も書いていますが)僕は日本で自分のいた環境がどうしても好きになれなくて飛び出してきた口なので、その長年募らせた思いと遂にそこから出てきたという解放感、そして新しいものに触れた刺激が一緒くたになった結果として「この調子で物事が進めばもっと大きなことも達成されるに違いない」という考えがあったのだと思います。確かにその認識は(少なくともその時点では)決して間違ってはいなかったし、そのように上を向けるのはとてもいいことでしょう。しかし裏を返すとそれは感情論に引っ張られた無計画性の現れでもありました。もちろん自分の主張は必ず論理立てて考えるように気を付けていたし、おかげで今見ても納得できるところの多いものになっていますが、そこに至る動機があまりに一面的過ぎたと少し反省しています。ただただ自分が好きになれずに残していったものをひっくり返したい、その結論ありきでしか物事を見れていなかったように思います。
そこに違和感を持ち始めたのが留学して1,2年を経た頃です。大学入学直前に書いた留学後2年レポートでは「時が経つにつれて単純に『逃げたい』ではなく『変えたい』へと思いが変わっていきました…(中略)しかし、現実問題として『どのように?』と考えた時そのハードルはとてつもなく高いということに気付き…(中略)ここまで考えが至った時に、はたと『本当に日本を変えようと努力すべきなのだろうか?』という疑問が生まれました」と、一歩引いた視点でものを見ようとしている様子が現れています。
それを経て今はどうかというと、「大局的なことは一旦脇に置いて、身近に目を向ける」という現実志向に落ち着きました。この大幅路線変更にももちろん動機が存在します。最も影響を与えたのは大学に入って以来さらに積み上がった経験値でしょう。この4年間、本当に様々な事態に遭遇してその度に新しい経験を積んできましたし、様々なものを目にもしてきました。経験を積むとは知識が増え、言動の引き出しが増え、対応できる場面が増えるということです。これらは一般にポジティヴに捉えられるでしょうが、その反面で「知る」が増えるとは「知らない」が減ると同値でもあります。知らないことが減るというのはそこにあった空白が埋まる、即ちその空白に存在していた様々な可能性が一つに収束すると言い換えることもできます。つまり経験とは一般に視野を広げる手段として持ち上げられますが、見方を変えるとそれはそこに在ったかもしれない可能性を削り見通しを狭めさせることにも繋がるのです。人はそれぞれ自分の考える世界というものを持っている訳ですが、その構成要素が一つ、また一つと経験という名の答え合わせを通して上書きされていくことは自分がまさに今見ている/認知している世界への確信を揺らがせます。時間を重ねて視点が増える度に「自分の見えている範囲なんて世界のほんの一部でしかない」というある種の達観を身に付けてしまうのです。これこそが冒頭の「世界観の変化」が意味していることです。
個人的な話に戻ると、僕はこの「実は自分は何も見えていないのだ」という感覚がどうしても拭えなくなって以来、以前のような主語を大きくした - 社会や国家の在り方についてといった - 論調を大幅に減らしました。自分が昔書いたものを否定するつもりは毛頭ないですが(我ながらよく書けてると思うところも沢山あります)、新しい見解や論を組み立てようとするとどうしても自分の見識や理由付けでは不十分なのではないかと考えてしまうようになったのです。また、この意識の変化の一因は数学科として常日頃から厳密性を気にするという癖にも隠されていると思います。既に述べたように、数学徒にとって主張の真偽とはきちんとした前提と証明が与えられて初めて判定できるものです。なので自分の持っている情報が不足していると思ってしまった時点で、そこから導かれる論の正当性すら自分の中では揺らいでしまうのです。
それを踏まえると、この段の始めに書いた「自分に社会は変えられない」という言葉の真意は「きちんと理解すらできていないものにあまつさえ手を加えようと考えることはできない」というところに落ち着くでしょう。つまり社会を変えたい云々の議論以前に自分はまだまだそこに至るための段階を踏めていないと再認識した、それゆえの「身近でできることをこなす」という方針な訳です。
4. 結論、そしてそれでも書く理由
ここまで、「書きたい欲」が減衰した理由について様々な考察をしてきました。改めてまとめると、新たな生活環境によって発達した内向性に加えて「自分には世界の一部しか見えていない」→「そんな前提が不足した状態では厳密で普遍的な論理が組み立てられない」→「不完全(かもしれない)な自分の論を他者に喧伝する気にはなれない」という一連の思考回路こそがこの問題の根幹に存在しているのだと考えられます。
世の中には自分の意見に自信を持てる人、自分の意見が絶対の正義ではないと思いつつもその対立を受容しながら発信する人、はたまた正義か否かは議論の対象ではないと考える人など様々な立場が存在します。その枠組みで言うと以前の僕は自分の信ずるところを積極的に発信する側の人間でしたが、ここ数年を経て「自分の経験を基に思索することはあれど、その結論の普遍性に確証が持てないので一般論へと帰納させることはしない」という何とも面倒くさい立ち位置に変わったことになります。その結果として、一般論としての考察文を書くことにも気後れを覚えてしまうのです。個々が己の限定的な経験に基づいて意見を戦わせる行為こそが集団社会の原点であると論じることもできますが、僕は普遍性/抽象性に重きを置くという価値基準を信念としているので、可能な限りそれらを追及していきたいと思っています。今回取り上げた変化とはそうした自分の中の軸に従った結果もたらされたものです。
もちろん考えることそのものを放棄したのではなく、方々に思索を巡らすことはあれどそれを他者と共有するかはまた別問題ということです。事実、前回・今回の両レポートにおいては個人の内面に焦点を当てて持論を展開しました。これは人格というトピックの性質からしてそもそも普遍かどうか(他の人が同じ結論に到達するか)気を配る必要があまりなかったからです。おかげでその方面での考察が捗ったので、これはこれで変化がもたらした肯定的な副産物と呼ぶことができます。
さて、ここまで読まれた方は皆揃って思っていることでしょう。「こいつ、『ものを書く気力が無くなってる』というテーマで9000字も書ける狂人なのか…」と。そのご指摘は甘んじて受け入れます。ラッセルもびっくりの自己言及パラドックスですね。ただ一つ強調しておきたいのは、あくまでここでの主題は「主義主張を文章を通して伝えたいという思いが消えてしまった」だけの話であって決して文章を書くという作業そのものから離れようとしている訳ではないということです。なのでひとたびテーマさえ与えられれば(たとえそれが「テーマがないことについて」だとしても)文章自体は嬉々として書くのです。
それに加えてもう一つ、今の僕がこれほど事細かく自分の考えを書き出している理由に「思考の記録」があります。思考とは刹那的なもので、一度過ぎた考えは放っておくと後から続く無数の他の思考によって押し流されてしまいます。そしてさらに時が経つと自分の考え方そのものが変化するので同じ思考は二度と取り戻せません。だからこそそれを留めるために本というものが生まれ、何度でも - 第三者によってさえ - 再現可能な客観的思考回路の集積所ともいえる音楽や科学という手法が重宝されるのでしょうが、個人の記憶という些細なものでさえそれらと等しく価値のあるものだと僕は思います。昔からなまじ記憶力が良かったせいで逆に「忘れる」ということに対して過剰な恐怖と反発心を持っているのですが、そんな自分だからこそこんな本気で思考を文章に落とし込むという作業に向き合えるのかもしれません。振り返ってみると、このレポートを書くにあたって一番役に立ったのも自分で書いた過去のレポートたちです。今回のメインテーマは「変化」でしたが、そうした変化を見て取れるのもここまで書き溜めてきたものがあるからこそなので、毎回長々と書いているレポートの存在意義がまた自分の中で立証されたのは嬉しい限りです。
大学生活もここで折り返しとなりました。財団のお世話になる残り2年の間にもまだまだたくさんの苦楽が待っているでしょう。その一つ一つを存分に満喫しつつ、そして最後には自分の変化とその過程を誇らしく見せられる人間になれるように決意を込めて、今回の結びとします。
