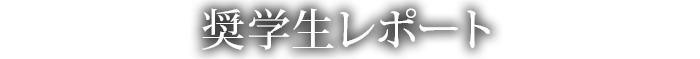
2020年のコロナ禍の中渡英し、イギリス生活が始まってから5年間が経ちました。5年目はIndustry Placement生としてArup (エンジニアコンサル会社) で一年間勤務し、多くの事を学びました。長文になってしまいましたが、今回のレポートではこの1年で得た経験と気づきを書いていこうと思います。
Industry Placement制度についてなぜPlacementを取ると決めた理由
Industry Placementとは一年間、大学に席を置きながらも会社にインターンとして勤務し経験を積む事ができる制度です。大学のコースによりますが、Durham大学では大学2年目にそのまま学士3年目に最終学年に上がるか、Placement制度で1年間インターンをするか選択することができます。Placement Year後は大学に戻りもう一年勉強し卒業になります。
私がIndustry Placementを取ると決めた理由は、就職の際に必要なスキルと経験を身につける為、持続可能的な社会形成や自然保全が促進されている中、実際に社会で注目されているまたこれから必要になっていく分野を見定めたいと思ったからです。理由の一つ目の就職に関してですが、大学の先輩のアドバイスやキャリアイベントに参加する中でイギリスの経験と実力重視のキャリア、就職活動に驚かされました。就労ビザの獲得条件が難しくなっていく中でインターンとして一年間働く事ができる経験は将来の就職の際に強みになると考えました。
第二の理由としては、これから必要になっていく分野と技術を見極めたいと思ったからです。Natural Sciencesコースを取っていく中で現在の地球温暖化や環境問題の深刻性またAcademicaの中で提案されている様々な解決策を学んできました。しかし、実際に社会の中で何が受け入れられ、環境の為にどんな活動が行われているのか見極めたいと感じていました。大学最終年度で専門性を高めていく中で、私自身の興味関心だけではなくこれから将来的に必要になっていくトピック、課題に特化していきたいと考えていました。このPlacement の中で私自身の目標にしている環境問題の改善に向けての道を選んでいきたいと思っています。
Industry placement先を見つけるのにはかなり苦労しました。受け入れ先が少ない中、環境系の会社に何社も応募し面接を受けようやくイギリスに本社がある国際エンジニアコンサル会社,Arup, の水事業のチームに働く事が決まりました。経験の幅を広げる為にもクライアントの課題を解決し、幅広いプロジェクトに関わる事ができるコンサル会社に興味を持ったのもArupを選んだきっかけです。また環境と広い分野の中で水という観点(レンズ)から自然と人間の共生の課題を見つけていきたいと思いオファーを受け入れました。
Placement 初期と働くことに慣れるまでの道のり
最初の三か月は正直、会社の仕組み、Full-timeで働く生活習慣、新しい街、チームに慣れるまで大変でした。特にArupはEmployee-owned Company (従業員所有企業)であり、一般的な株式会社と違いすべての会社の所有権は従業員自身にあります。そのためArupの仕組みや方針の決め方、チーム構成を理解するのに時間がかかりました。しかし、私たち従業員一人一人が自身の意見を上層部へ直接共有でき、どのように会社を成長させていきたいか協議し、選択できる仕組みに魅力を感じました。
全くイギリスの水道治水の知識がない中で働き始め、複雑なWater Industryを理解するのに苦労しました。イギリスの水道事業は国営ではなく私営事業として各地方によって全く仕組みが異なり、治水事業は深刻化する洪水、水不足、水質汚染問題に対して法律やポリシーがすぐに変更されます。正直に知識が足りないから不安だとチームに打ち明け、おすすめの本、記事、サイトを読むことで少しずつ理解することができました。けれど何度も言われたのは、「プロジェクトを通して学ぶことが一番だ。先輩自身も毎回新しいプロジェクトに関わる度に学ぶこと初めて知ることがある。」その言葉のおかげですべて完璧に理解する必要はない、柔軟に対応し学んでいくことが大切だと学び、前向きな気持ちで新しいプロジェクトに取り組む事ができました。
Full-timeとして働くライフスタイルに慣れることも大変でした。コンサルタントとして働く中で決まった業務は無く、どれだけ忙しいかまたどのようなプロジェクトに関わることができるか全く読めません。週の初めは仕事が無いと探し回っていたらと思ったら、次の日には仕事に追われるなどその日その時の状況に柔軟に対応していくことに一杯一杯でした。どのようなプロジェクトに携われるかも、何をやりたいと自分から声を上げるか、会社内のネットワーク次第で仕事を手繰り寄せる必要があります。先輩もよく仰っていたのですが、”You need to be at right place at right time.” 面白い事業で働くには運と常に自分から探していく必要があるとしみじみと実感しました。時期によっては全く仕事が無い時もあり、そのような中で自分自身のモチベーションを維持する為に記事を読んだり会社内の異なる部署の方々に今までの皆さんのキャリアやアドバイスを聞いて回ったりしました。最初の三か月はこのようなワークライフに慣れるまで大変でしたが、少しずつ会社やオフィス内でネットワーク、繋がりを築いていくことで様々なプロジェクトまた将来のキャリアについて学ぶことができました。
Placement4か月目以降の気づきと考え方の変化
一番Arupで働き始めてから私自身変わったと感じていることは物事に対する視点と考え方の変化です。私が所属しているチームは主にクライアントの課題、問題に対してより持続可能な、自然環境、人々の生活に最適な解決策を探し出す,Decision-making & Total-value,を主に活動しています。
例えば、私が長く働いた事業の一つはAdaptive Pathway Planningを世界の治水事業で始めて導入しました。 気候変動、人口増加、経済成長など将来の不確かな点が多い中で、最も最適な治水、利水事業は何か試行し20年後50年後になっても経済と環境の変化に対応できる、Adaptive Planning 長期開発計画を作成しました。このプロジェクトでは地球温暖化や地域の経済成長の推測モデルを作成し、将来のRiskとOpportunityを事前に理解し逆算することで、今何をすることが最も後悔のない将来に最大限の利益をのこすことができる、No-regret Options,を見つけ出すことができました。
他にも、いかに幅広い経済、自然への利益を優先できるかまた長期的な利益を先読みし計画できるか、Total-Value Frameworkを使い利益とコストをTrade-Offしてクライアントの事業戦略計画の助けをしていきました。一つのプロジェクトの例としては、水不足が深刻化しているイギリス南部では新しい貯水場や北部からLondonへ水を運搬する計画が始まっています。コストや主な水の供給量を増やすことだけに注目するとコンクリート製の何の変哲もないデザインが採用されてしまいます。そんな時に私たちが従来のデザインではなく自然を使った解決策、Nature-Based Solutions やダムに新しい湿地帯公園を隣接することで新しい野生動物の住処と人々にグリーンスペースを提供できる。これらから得られる長期的生態系、経済的利益を数値化することで投資家や開発者にただ短期的、コストを主にした考え方からより持続的な解決策を行うことを説得できました。
このようなプロジェクトに関わり、リサーチ、またクライアントと話し合っていく中で私自身、本当の意味の持続可能な未来とは何か、長期的な考え方、一つの問題をそれを取り巻くシステムから理解することで根本的な原因を見つけていく”System-thinking”を身に着けて、理解することができました。
Placement 最後の4か月間
Placement 8ヵ月目から、私の中で仕事に対する自信とチームメンバーから信頼を感じ始めました。様々なプロジェクトで働くことで私自身の強み、複雑な物事を図化しシンプルなものにして行くこと、プログラミング能力、レポート読解力を生かし伸ばすことができました。また私自身、Sciencesだけではなく政治や経済的考え方また重要性を実感し私なりに学び始めました。
特にイギリスの外務・英連邦・開発省と方々とプロジェクトに携わったことにより、いかにポリシーの重要性と幅広い視点の大切さを学ぶことができました。私が携わったプロジェクトはイギリスの国際支援と開発に関わることで国や都市を異なる6つの視点、PESTLE(Politics, Economic, Social, Technology, Legal, Environment)で調査しこれから水不足が深刻化する国々にどのような支援とサポートが最適か実際にその国の方々と話し合いながらレポートを制作しました。他国の水問題、環境問題また水事業を学び、水の役割と影響を異なる観点から調べていくことは物事を多面的に見ることの重要性を学ばせてくれました。このレポートは後日、政府から民間に公開される予定でチームで協力して作っていったものが広く公開されることにとても嬉しく感じています。
イギリスと世界各国の水問題と治水水道事業について学ぶ中で、日本の現状に興味を持ち始めました。日本の治水事業の歴史と現在の活動を調べていく中で日本の古くからの知恵、推進的な取り組みを知りました。イギリスと日本で地理や環境が異なる中でも似たようなアプローチや解決策が沢山あることに驚きました。この発見をチーム会議で共有することができ、同僚の方々も日本の活動から学ぶことがあると言っていました。イギリスにいながらも、これからも日本や世界各国の取り組みを学んでいきたいと思います。
培った自信とチームからの信頼を得たおかげで更に異なる事業に関わることができました。イギリスでは新たにNature Marketと言って、生態系サービスをトレードするマーケットを開き新たに自然を保全し、自然から得られる恩恵を地域経済の為に守っていく取り組みが始まっています。その中で、新しく水源、水質改善と治水量をクレジットとして水マーケットをBristol地域で試行するプロジェクトに参加しました。今までマーケット構成などの経済学など学んだことがなかったのですが、チームの先輩からアドバイスや記事を読んでいく中で理解することができました。今までの私の主な興味は自然保全や自然を活用していくプロジェクトでした。自然と共に働くことは時間がかかり、効果を確実に予測するのは不可能です。このプロジェクトで、いかに長期資金源の確保の大切さまた、そのような自然保全事業が助成金のみに頼らず自立して長期にわたって成長するためにこのようなNature Financeの大切さを学びました。
イギリスでの働く環境とワークライフバランス
今までのレポートがかなりテクニカルな内容になってしまいました。この段落では私が感じたイギリスでの働く環境とサポートまたライフ面での一年を簡潔に振り替えたらと思います。
一番初めに驚いたことはチームのフレンドリーさと活発な社内サークルの活動です。ランチタイムには皆で公園に行きお弁当を食べたり、給料日は皆でパブに行ったり、毎週水曜日には週替わりでチームの一人が手作りケーキを持ってきてたべたり(この手作りケーキのできがチーム内の評価に重要⁈)など働く環境とチームの雰囲気の良さに恵まれました。社内でも、会社内の人を選出して異なるチームのプロジェクトや会社の方針を話し合う場がランチタイムにあり、水チーム以外のArupのメンバーと知り合える機会が沢山ありました。社内サークルでは、室内ボルダリング、サーフィン、フットボール(サッカー)に参加しました。会社からボルダリング代の一部やを負担していただいたり、フットボールのトレーニング場の提供や社内サークルでの旅行の補助などサポートを沢山いだたきました。サーフィンでは10月末にイギリス西部のNewquayに各地のオフィスから80人が参加し皆でハロウィーンにちなんで仮装大会とサーフィンレッスン。ボルダリングではWalesの北部のスノドニアで3泊4日のキャンプをしながら人生初、屋外で本物の”岩のぼり”をサークルの皆で楽しみました。
2か月に一度、水のチームでTeam Socialイベントが行われ上司や同僚と一緒に夕食を食べにいったり、ボルダリングをしたり、陶器作りをしたり、ボートに乗って運河を渡ったりととても楽しかったです。新入社員の同僚と一緒にクリスマスパーティーを企画するのはなかなか大変でしたが、チーム一人一人とさらに仲を深めらることができました。
会社内での社員同士のサポート、Diversity&Inclusionの活動にも驚かされました。世界各国にオフィスがあるArupではもちろん働くメンバーのバックグランドも様々です。各メンバーがそれぞれのアイデンティティや文化を受け入れ共有できるよう、ArupではConnect Out というコミュニティーがあります。私はこの活動に活発に参加する中で、Diversity(多様性)とInclusion(受容)の重要性と会社のメンバーが理解し行動していくことが最高の職場の環境とチームを作ることに繋がると実感しました。私が主に参加した活動を並べてみました。
Connect Out Women Community:エンジニアリングは未だ主に男性が多く占める業界です。Arupで活躍する女性エンジニアやトップの組織にいる女性の方々も沢山いますが、まだまだ改善できる点はあります。女性としてキャリアと家族どちらかを選択することなく、また性別関係なく働ける環境づくりを日々話し合う場がありました。実際に女性メンバーの方々の経験や意見を交換する中で沢山のキャリアや女性の人生選択に関するアドバイスを頂きました。
Connect Out Culture Community:イギリスで誕生し本社を置くArupではやはり、アジアやアフリカ、南アメリカ系のメンバーは少数です。Bristolの水チームでは私を除いてすべてのメンバーがイギリス出身でした。イギリスの文化、習慣、生活に沿って主に会社が運営されている中で、多文化の理解や習慣の違いを共有し広めていくことを目的としたこのコミュニティー。私も日本人として祝い事の違いや文化、歴史をディスカッションの場で共有しました。その中でユガンダ、インドから働きに来られた方々から移民としてイギリスで働くことの経験や難しさなど沢山の学びがありました。
Connect Out LGBTQ+ : 各メンバーがそれぞれのジェンダーで差別されることなく、オープンに働ける場作りを目的としたコミュニティーです。センシティブな話だからと避けられることが多い話題ですが、自分はこうだと誰かに差別されることなくありのままでいられる環境がいかに大切か沢山のLGBTQ+メンバーから伺いました。まずは周りが理解しこうあるべきという概念を捨て、違いを受け入れる環境づくりをAlly(味方)としてデスカッションに参加したり、プライドパレードに参加したりと積極的に行いました。
これから
まだまだ完璧ではありませんが、イギリスの水道治水事業や世界でのこれからの課題について考え私なりにこれから何が必要になっていくのか見つけ出すことができました。大学に戻り、学生だからこそある自由と時間を使ってこれから必要になっていくスキルと知識を蓄え伸ばしていきたいと思います。
私自身、研究が好きで大学などの研究機関の道に進むことも考えていましたが、今はまず現場に行き経験を積める会社で働きたいと思っています。特にArupで働いて実感したのが現在のAcademia(研究機関)とIndustry(産業)のギャップです。大学で学んだこととIndustryで今一番必要されていることの違いと差を感じました。まずは業界に入って働くことで私自身の強みを知り、社会のニーズ、私自身の興味を伸ばす中で、私にとって最適な専門分野をみつけ修士を取れたらと考えています。
Arupに入ってきたときの最初の主な興味は自然保全とNature-Based Solutions でした。しかし、現在の水問題また水の自然環境、経済、人々の暮らしにおける重要性を理解したことで自然環境の中で水という分野に注目して”人と自然が助け合い共生できる場”を作っていけたらと考えています。
最後に、この一年で沢山学び成長することが出来ました。このような素晴らしい機会をくださったTazaki財団のみなさん、辛い時に支えてくれた家族、友達、そして沢山の事を教えてくださったArupの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これから大学に戻り、奨学生として最後の一年間を最大限に活用できるようこれから精進していきたいと思います。
