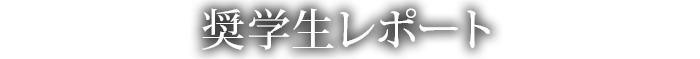Kさん(University College London, Economics / Kingswood School出身)
2018年11月。日本、家族と暮らす東京の自宅。西日が差し込む勉強部屋で、tazaki 財団への応募を決めた。第一志望の高校に入学してから半年、友達も多く、充実した毎日。部活動や学校帰りに飲むタピオカが日常のハイライトで、中学校の時から憧れていたキラキラした女子高校生生活には何の不満もなく、毎日が楽しかった。輝かしい未来に繋がっているレールの上を順調に進んでいるようだった。だが、心の底には時代を切り開き、新しいことを始めることへの憧れがあった。明るい未来が担保された「正解」を選ぶのではなく、自分の頭で考え、行動し、世の中を変革していく人生。そんなドラマチックな人生に憧れ、このまま「幸せ」のレールを歩いていては、何者にもなれないのではないかとたまらなく恐ろしかった。
6年後。2024年12月。イギリス、大学の友人と暮らすロンドンのフラット。朝日の差し込む自室で、第一志望のコンサルティングファームからいただいた内定を承諾することを決めた。優秀な仲間と意義のある仕事をし、不自由のない生活が担保された未来。財団に応募した際、イギリス留学という「挑戦」を選んだ私は、6年後、「正解」を選んだかのように思える。私の中の挑戦を求める炎は消えてしまったのだろうか。しかし、この選択の違いこそが、私が留学生活で築いた信念と精神的成熟の帰着点だ。何をしたいかがなく、ただ漠然と異なる環境に踏み出したいと思っていた17歳の私には、挑戦とは何か、他人の尺度で測ることしかできなかった。挑戦とは、レールから外れる選択をすることだと考えていた。だが今は違う。人には一人ひとり歴史があり、目指すものがある。それぞれが自らの目指す未来に向けて選択し、道を作っている。そこにレールは存在しない。その道、その選択は、その人だけのものだ。手段が同じでも、目指しているものが違えばたどり着く場所は変わる。私の選んだ「就職」という道は、現在の自分の能力と知識の限り、私のやりたいことを実現し、なりたい自分になるうえで最も近道だと考えている。
前置きが長くなってしまったが、最後のレポートである今回は、「やりたいこと」が明確になかった私が留学を通じて見つけた、「やりたいこと」「なりたい自分像」について書きたいと思う。
やりたいこと:脱炭素社会の実現を通じて日本、そして世界に貢献する
初めて渡英してから帰国するまでの6年間は、自分が何のために生まれてきたのかを考え続けた時間だった。頭の中には、壮行会での田崎理事長の言葉があった。恵まれた機会を与えられたからには、そこでの成果を社会に還元してほしい。その言葉に私は感銘を受け、今、社会で何が求められているのか、自分に何ができるのか、自問自答の日々だった。パブリックスクールでの2年間は、学部選択やパーソナルステイトメントの準備を通じて否が応でも何に興味を持っているのか、常に問い続けることができた。経済について勉強する中、環境経済という分野の存在を知った。脱炭素社会の実現が喫緊の課題であること、脱炭素と経済成長はトレードオフではないという考えに衝撃を受け、ヨーロッパで進んでいる脱炭素に向けたルール作りに日本が乗り遅れていることを知った。これだ、と思った。留学経験を活かし、日本の脱炭素化に貢献することで、日本に、ひいては地球市民として世界に貢献する。私に与えられた使命だと思った。脱炭素とひとくくりにしても、技術開発、政治側からのルールメイキング、ビジネス、金融など様々なアプローチがある。私は自分に適性があると感じたビジネスフィールドに身を置こうと考え、大学で経済と経営を学ぶことを志した。大学入学後はenvironmental economics societyへの参加、環境系スタートアップ設立のための市場調査、排出量取引に関するレポートの作成、電力会社の駐在員の方との交流など、様々なことを行なった。次に繋がる経験もあれば、そうでないこともあったが、やってみることで問題に関する解像度が高まり、脱炭素の中でどの分野で専門性を持ちたいのか、高い粒度で考えられるようになった。また、やるべきことがある程度決まっている高校とは異なり、全てが自主性に委ねられている大学生活を通じ、時間が有限であることを痛感した。限られた人生において脱炭素化に貢献するためにインパクトの大きな分野に注力したい、と考え、エネルギー分野に関心を持った。脱炭素テック企業でのインターンを通じ、業界について詳しくなればなるほど、ビジネスチャンスの大きさにワクワクし、同時に既存システムの堅固さや政治情勢などの不確実性、資本や技術の必要性を痛感した。また、インターン先ベンチャー企業の創業者の生き方を間近で見たことで、My Company = I として、会社を通じて人生の目的を達成するキャリアに魅力を感じた。インパクトの大きさを考えると、資本の大きな会社のエネルギー部門で働くことも選択肢のひとつだ。一方で、手触り感を持って事業を運営していく働き方を選ぶならば起業やベンチャー企業といった選択肢もある。これらの中で最も挑戦的なキャリアは起業だろう。経験のなさが越えられないハードルではないことは、若いうちに起業して社会にインパクトを与えている人々が実証している。成功のために必要な人脈や知識、資金は自分で積み上げるものだ。やれない理由を探すのではなくその環境でやれることを考える、コロナ禍で培ったこの考え方は私の価値観の支柱のひとつだ。起業という選択肢を考えず、就職することは、経験のなさを「やれない理由」として挑戦を諦めているかのようで、過去の自分への後ろめたさがあった。しかし、この後ろめたさは憧れやプライドによるもので、脱炭素化に寄与するというミッションの前では小さなものだ。興味分野でのプロジェクトの多いコンサルティングファームへの就職は、業界のプレイヤーやルールを把握するうえでかけがえのない経験となり、将来、挑戦を目指す私の背中を押すだろう。人生を通じた社会へのインパクトを最大化するため、就職を通じて自身をもっと武装したいと考えた。「やりたいこと」がないままに成長を求めて留学を決意した17歳の私と、「やりたいこと」を達成するために、将来の進む道を選択した自分の変化は、歓迎すべきことだと納得している。どんな道を進むにせよ、それを自分にとっての正解にするのは自分自身だ。オックスフォード大学に落ち、UCLに入学したことを正解にしたのと同じように、コンサルティングファームに就職する選択が今後に資するものになるよう、1日1日を大切に生きたい。
なりたい自分:Giver-与える人
パブリックスクールでの2年間はひたすらに自分のことで手一杯だった。新しい環境への適応、英語力の向上、勉強、課外活動など、先輩や家族、ホストファミリーや先生の助けを借りるばかりで周りをサポートする余裕がなかった。高校卒業後、ギャップイヤー中に少しだけ在籍していた学生団体のアラムナイとの出会いが私の考えを変えた。彼は自身の仕事もある中、毎週団体に顔を出し、後輩の育成に努めていた。「社会を変える人材のネットワーク」を作ることを目指し、時間と労力を惜しみなく使う彼の志に、田崎理事長の理念とつながるものを感じ、私と10も歳の違わない先輩の姿に感銘を受けた。田崎理事長や彼は、まさに一流は人を残すという言葉を体現しているかのようで、私も人を残せる人になりたいと憧れた。自分の成功は、ひとりで努力した結果だと思ってしまいがちだが、私の今は、先輩方から引き上げてもらったからである。恩に報いるためにも、憧れる彼らに近づくためにも、Giver になりたい。しかし、1人が与えられるものには限りがある。一人ひとりが異なる専門性を持つコミュニティで共助しあうことで、後輩たちが巨人の肩に立つ土壌をつくることができる。1人では起こせない変化を、次の世代が、さらに次の世代が起こすことができるかもしれない。そう信じて、tazaki財団コミュニティ(TFコミュニティ)の世話人として、オンライン、オフラインでの交流の場を設け、財団生同士の気軽なコミュニケーションを実現するプラットフォームをつくった。この経験はなりたい自分に近づくための第一歩だったと考えている。今後はアラムナイとして、TFコミュニティのみでなくさまざまな場所で人に与えることができる人になりたい。また、与えるためには、自分自身が知識や経験を持っている必要がある。そのためにも日々貪欲に成長したい。
以上が、留学生活を通じて見出したやりたいこととなりたい自分像である。これらは今後も私の意思決定の指針となるだろう。核となるものを見つけることができたのは、様々な形で私を支え、刺激を与えてくれた方々のおかげだ。田崎理事長、財団事務局の皆さん、三期生の同期、一期、二期の先輩、コミュニティ設立にあたってたくさん刺激をくれた四期から六期の後輩、日本からずっと支え続けてくれた家族、日英の友人には感謝してもしきれない。6年間、本当にありがとうございました。与えていただいた機会を生かし、今後は私が社会に還元してまいります。今後ともよろしくお願いします。