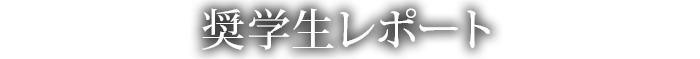
アーサーの玉座(Arthur's Seat)を包む淡色の空模様をエディンバラ大学の図書館から眺めつつこのレポートを書くことが私にとって夏の終わりを告げるものでしたが、今年はロンドンにある大学図書館にて、木々を燦めかせる日光の下の雨粒に心を奪われつつパソコンと向き合っています。人生についてくる変化という名の時の不可逆性を身に染みて感じつつ、早いものでレポートを書く機会も今回で最後になってしまったことが大変悲しまれるこの頃です。さて、大学も四年目ともなると生活面での目新しいことは特筆するほどではないかと思います。その代わり今年度・留学全体・そしてこれからについて、学問に関わる話を出発点に書いていこうと思います。(注:最終回だと思って書いたら今までの私のレポートに類を見ない長さになってしまいました。読まれる場合は心して、お茶でも沸かされてから始められますよう。)
1. 今年の思い出—エッセイと卒論
ここ数年の大学生活を通して、私は視覚・物質文化を通して集団のアイデンティティはどのように表現され、構築された、そしてされるのか、ということに興味を持つようになりました。昨年まではスコットランドを含むヨーロッパの国いくつかについてこのような観点で勉強をしたのですが、今年は、特に一学期、ソ連を中心とした20 世紀の社会主義建築と18世紀-20世紀初頭の南アジアの美術といったヨーロッパを超えた文化地域に目を向けた授業を取りました。特に思い出深いのは、“Architectures of Socialism” という講座で書いたエッセイです。1939年と1954年に開会されたソ連の全連邦農業展覧会 (昔の万博の国内版のようなものを思い浮かべると遠からずかと思います) におけるソ連内の共和国ごとのパビリオンの建築や展覧会全体のデザインを分析し、ソ連内における「中心」(特にロシア)と「周縁」(ここではケーススタディとしてウズベク・ソビエト共和国など)の概念の変化について論じました。長くなるので詳しい説明は避けますが、これについて西ヨーロッパの国などに比べ特に興味深かったことは「西側」「東側」という二つの概念—若しくは二つの自身を比べる対象としての「他者」—の重要性です(注:これらの概念は冷戦中の「西側」・「東側」と必ずしも一致するものではありません)。ソ連の内側と外側にそれぞれ存在する「西」と「東」がどのように国のアイデンティティ形成・変化と関わっているのか、建築的な表象を通して分析したこのエッセイは、先生から「若干の推敲を加えればぜひこれを学術誌で読みたい」とのコメントをいただくことをできました。学部を卒業する前になんらかの課題で “publishable” の言葉を頂戴することを内心の目標としていたので、ここでこれを達成できたことは大変嬉しかったです。
そしてその評価以上に重要であったのは、期せずしてこれが卒業論文に繋がっていくこととなったことです。下学年だったうちから卒論を書くことはずっと楽しみにしていたのですが、いざ始めようとなると一つの「これぞ」というテーマを決めることがなかなか難しいものでした (私が優柔不断なだけな可能性も重々ありますが)。一学期の間、19-20 世紀の博物館建築における何らかのアイデンティティ表象についてやろうということ以上なかなか納得のいく問題提起ができず、霧の中を彷徨っているような気持ちで過ごしていました。しかしこのエッセイを書き、また南アジア美術の講座でオリエンタリズム批判について多く学んだのち、ロシアにおける「東」、ヨーロッパから見た「オリエント」、そして日本語に存在する「東洋」という概念のズレ・違いに考えが及びました。そしてこの「東洋」という概念が明治以降に作られたものであり、またこの言葉が博物館や建築に関わるものを含む帝国時代の日本の文献にやたらと目につくと気がついたとき、この「西 / 西洋」と「東 / 東洋」という二つの「他者」の存在は、ソ連だけでなく日本のアイデンティティ構築の分析ツールとしても重要なのではないかと思いあたったのです。さらに、実際20世紀初頭の建築の一次文献に登場する「日本らしいもの」と「東洋的なもの」という二つの概念の関係性がどうも21世紀を生きる私には簡単に飲み込めなかったことから、ここには何か深掘りできるものがあると感じました。これをきっかけに—詳細について書いていると長くなってしまい最早卒論を読んでもらった方が早いので省略しますが—これは掘り下げる意味と価値があると確信できた問いを見つけ、その後は締切までの2-3ヶ月、ほぼ卒論のことしか考えずに過ごしました。テーマ決定が遅くぎりぎりまでこれは本当に終わるのか不安がなくはなかったものの、何とか完成に漕ぎ着けることができました。「近代帝国日本における『東洋』像」と題したこの卒論は—改善点は多々あるとは思いますし、将来的に見れば未熟さを恥ずかしく思うくらいになるべきでしょうが—これまでの人生の中であまりなかった、これは本当に頑張ってやったと自信を持って言える経験となりました。
2. 話を少し広げて—留学を振り返る
卒論を書いている期間は、あれを読もうこれを読まねばそれも読もうか、と卒論をそれ自体もしくは学術の世界の枠組みの中でしか考えを巡らせる余裕はありませんでした。しかし夏休みという(旅行、サマースクール、TOPSのサポート、アーカイブでの仕事と盛りだくさんだったものの)精神的にかなりゆとりのある時間を過ごした今、この経験を私の留学全体、若しくはもっと長い目で見たこれまでとこれからの私自身のうちにどのように位置づけられるのか、ということについても思惟することが少しはできたと思います。留学全体のレポートの意味を兼ね、ここに少し記録しておきたいと思います。
卒論のテーマを探していた時、日本の建築に関わることをやったらいいと複数の先生に言われたものの、私は安直にそれをテーマに選ぶことに躊躇がありました。こちらにいる人からすれば、日本の建築は (少なくとも英語圏では) 研究が少ないので穴が多いし、せっかく日本語の一次資料を読むことができるという多大なるアドバンテージがあるのだからなぜやらないの、と思うのでしょう。しかし私はそのとき、日本の建築を研究することは、まるで「日本人だから」日本の建築をやるとでもいうような、それこそ自分のアイデンティティが「日本人」であることだけに吸収されてしまうような感覚を拭うことができませんでした。これは個人的な感覚の話ですが、確かに私は nationality も ethnicity も日本人ですがだからと言って国家や民族に強い帰属意識があるわけではなく、ならイギリスにあるかと言われるとそういうわけでもありません。言葉にするならば「日本語が第一言語で英語が第二言語で山口と東京とバースとエディンバラにいたことのあるいち地球の住人」くらいの感覚で、そしてそれ以上に自分の好きなことや興味のあることが自分らしさを規定していると思っています。それに、私が建築史に興味を持ったのはイギリスに来て古い建物に囲まれて暮らすという経験をしたからでもあります。しかし同時に、長い目で研究をすることを考えた時、英語に似ても似つかない、やたらと複雑な正書法を持つ日本語を第一言語として使いこなせるというのは—脱西洋中心主義の潮流の強いアカデミアの時勢を考えても—私が持っている一番のアドバンテージであることは間違いありません。競争の厳しい世界で、それを使わないという手はほぼないでしょう。もちろん、アドバイスをくれた先生方も別に国籍やら何やらに結びつけていたわけではなく、私の持っているスキルセットとしての言語能力や、ユニークなバックグラウンドを持つことによる新しい視点をもたらせる可能性について言っていたわけです。とはいえ、明確な研究計画を持ったもとで始める修士や博士課程と違い、学部の卒論は将来したい研究に結びついている必要は必ずしもありません。せっかく英語の文献も読めるようになったしここはあえて他のことをやるチャンスなのではないか、などとも考えました。そんなこんなでなかなか腑に落ちる決断ができず、折衷案として日英の比較研究にしようかなどと考えていた時もあるのですが、結果として日本にある一つの建築にだけ絞って研究することになりました。ここまで書いたようだともしかして私には一抹の苦々しさが残っているのでは、と思われるかもしれません。しかし思い返すと、これは「私の卒論はこうあるべきであった」とでも言うべき、留学を含む今までの学びの一つの終着点にして通過点— the dissertation of mine —と呼べるものになったと自負しています。
少し噛み砕いて言うと、まずスコットランドという、長きにわたり存在感の大きすぎる隣人たるイングランドを比べる対象としての「他者」として自らのアイデンティティーを形成してきた、またその違いに重要性を見出してきた国で暮らし、学ぶという経験をしたことは、そもそもナショナルアイデンティティについて興味を持つきっかけとして外せないでしょう。そして日本のアイデンティティの構築について考えを及ばせることは、留学という形で一旦日本社会を出て外側からの視点を持つ機会がなければまず出てこなかったものでした。さらに、日本における「東洋」という概念について考えることは、日本から見た例えば他の東アジアの国のイメージであったり、日本社会における言説をある程度理解していなければなかなか分かりづらいことであると思います。つまり、このトピックは「日本人」であること自体ではなく、日本でかなりものを考えられる年齢になるまで暮らしてからイギリス / スコットランドに留学したという「経験」を通して考え付いたものだと言えるでしょう。さらに、この論文を形作る視点の一つに「言葉とモノの翻訳」があります。留学前から私は言葉や言語に関心があったのですが、二つの言語を使って暮らし考えるようになったことによって特に、翻訳可能性・不可能性などを含む言葉への興味が強くなったと感じていました。必ずしもそのような興味は建築につながるものではないと思っていましたが、結果的にそれが図らずとも卒論に組み込まれたわけです。一言で言えば、この卒論は私が「日本人だから」書いた・書けたのではなく、(大袈裟に聞こえますが) 私の今までの人生の道のりがあったから書けたものだということです。そしてこう考えると「ユニークな視点」という言葉の意味が腑に落ちる気がします。外国人であることに何か本質的な異質性があるから「ユニーク」なわけではなく、今までの経験とそれに関わる思考という道のりの積み重ねによってユニークさが生まれる、ということです。
3. 話をさらに広げて—「ユニークな視点」とは何なのか
さて、この「経験と思考の道のりによって生まれる『ユニークな視点』」について、最近感じ考えたことを付け足しておきたいと思います。まず考えたい問いは、「ユニークな視点」は外的に規定されているのか、それとも外的な規定から自由なのか、と言うことです。分かりやすく言うと、もし私と同じ外的 = 社会的な条件で生きた個人がいたら (例えば学校、出身地域、居住歴、経済的背景、ジェンダー、国籍etc. など) 、その人は私と全く同じものの見方をするのでしょうか。その人は私と全く同じ卒論を書くのでしょうか。多分違うと思いますし、多くの人が私と同じように思うはずです。自分で決められない条件が同じでも、人はある程度の自由な思考を持っているわけで、同じ経験から考えることも違います。※1 つまり「経験と『思考』の道のり」が変わってくるわけです。では個人の視点は、そのような外的条件から完全に自由なのでしょうか?これもまた違う、と多くの人が特に疑問なく思うと思います。簡単にいえば、日本でずっと育った個人とイギリスでずっと育った個人は違うものの見方をする、と言うことは「異文化理解」と言う言葉が存在していることからも分かります。二つの違う文化圏で育ったそれぞれは違う経験を重ねてきているため、当然「『経験』と思考の道のり」は違います。さて、この二つの問いへの答えを踏まえたとき、「ユニークな視点」と外的条件 (= 社会とその個人の関係) の関係性はどう説明されるべきでしょうか ?
哲学者の國分功一郎はその著書『中動態の世界』の中で「言語は思考を直接に規定しているわけではない」が「言語は思考の可能性の条件を規定する」と述べていましたが、私はこの言語と思考の関係性を私の立てた問いにも応用することができるのではないかと考えます。(※1)つまり「社会と個人の関係はその個人の、経験と思考の道のりによって形作られた視点を直接に規定しているわけではない(同じ社会的条件に生まれた個人は同じ考え方をするようになるわけではない)が、前者は後者の可能性の条件を規定する」と言うことです。例えば日本社会に生きている人々が皆全く同じ考え方をするかと言われればそれは当然否ですが、その個人らが例えばイギリスにずっと暮らしている個人と同じ視点を持つことは起こり得ないのであり、それは「日本社会」によって存在がゆるされている範囲内の経験に基づいてその視点が形作られるからです。ここから言えることはいろいろとあり、また議論をもっと揺るぎないものとするにはさまざまにふさぐべき穴があるとは思いますが、とりあえずこの考えと私自身の経験をつなげていくつかの点を述べておきたいと思います。
※1 國分功一郎『中動態の世界:意思と責任の考古学 (文庫版)』新潮社 、2025年、178-179頁
まずは留学という経験について。例えば「日本社会に暮らす」だったり「イギリス社会に暮らす」といった「個人-社会間の関係」が、個人の視点の可能性の条件を規定しているものなのだとすれば、二つ以上の文化社会に暮らすことはこの視点の可能性を広げると言うことになるでしょう。例えば外国語を学習することのメリットとして「視野が広がる」ということがよく言われるのは多くの人が承知する通りだと思います。とある言語に存在しない時制、存在しない概念を他言語を通して学ぶことは、ものの見方の可能性を広げます。(私が言語学習を好きな理由も元を辿るとここにあると思います。) それと同じように、そしてそれ以上に、異文化社会で暮らすということはそれまでになかった経験をたくさんするということであり、それによって生まれる思考によって今までその個人に存在しなかったものの見方が生まれることと言えるでしょう。つまり、立つことの可能な視座の可能性が広がるわけです。(注:もちろん、広がるといってもこれは単純に1+1=2倍に広がるというわけではないと思います。ある経験に対する思考はあくまで、それ以前の経験と思考によって作られてきたその時点での視点に基づいて生まれるでしょうから。しかし、ここでその複雑な仕組みについて考えを及ばせることは避けておきます。)それこそが留学の醍醐味であり、最大の意義であると言えるでしょう。
二つ目は「社会的な条件」についてもう少し。ここまで私は、あえて決して「社会的な条件」と「その個人の生きる国などを単位とする文化社会」を=で結ぶことはしませんでした。他国への留学と関わることなのでどうしても国単位での社会条件の例を多く出したものの、それは「社会的な条件」の一部分にすぎないと言うことが伝わるように書いたつもりです。なぜなら個人-社会間の関係のうちに、「任意の国という文化社会」(文化圏と国家の範囲はイコールでないことの方が多いのですが、日本の場合は珍しく近似しているので話をわかりやすくするためにいったんこのように表現します)という一つの条件が果たす役割は、重要であるものの全てではないからです。例えば個人が社会から「女性」として扱われるか「男性」として扱われるか、経済的余裕のある暮らしをしてきたか否か、などなどなどあげ出すとキリがありませんが、そのようなさまざまな条件によって、個人-社会間の関係性は同じ文化社会圏のうちであっても大きく変わります。近年話題に上がる「インターセクショナリティ」の議論です。そしてそれゆえ、個人個人の経験は変わり、つまりものの見方も変わってくるわけで、それらさまざまな条件が重なり合って「個人の視点の可能性の条件は規定されている」と言えるでしょう。 だからこそ、(前述の通り、その可能性の範囲に違いがあるにせよ)留学経験の有無に関わらず個人個人はそれぞれ違う「ユニークな視点」を持っているのであるし、だからこそ人々はそもそもに多様であり、さまざまな視点の存在によって社会を面白くしていくために人々が多様であること、それを祝福すべきこととして社会が受け取っていくことが必要なわけです (ここで社会をよくする、という言葉を使おうかと思ったのですが、「良い社会」とは何かを考えることは流石に長くなりすぎるのでいったんやめておきます)。そして同時に、国家、ひいては民族単位で人間をまとめて見ることがはらむ危険性も重々伝わると思います。確かにそれらはある社会のあり方を決定する上で大きな役割を果たしていて、そして結果としてその社会と関係のある個人の「視点の可能性」を決定する上でも重要であることは間違いありません。しかしそれだけが「視点の可能性」を決定しているわけではなく、その一部でしかないと先ほど述べました。そしてそれはつまり、国家・国民・民族などというものは人々の間に共通項を見出し人々をグループ化するときの「一つの」方法であるだけでそれ以上でもそれ以下でもないということです (a way であるけれど the way ではないのです)。(そもそも、ナショナルアイデンティティ研究、文化的ナショナリズムの研究というのは、任意の国の国民はこうでありこうあるべきという一つイメージがなんなのかではなく、どうやってその形成が社会のうちに行われるのかということを考えるものです。こういうことを日常的に考えていると嫌でも国民やら民族やらの概念をやたらと押し出してくるレトリックには批判的になります。)このように個人の視点について考えることは、いかに誤ったレトリックが、人々がみな持っている違いに見ないふりをし、存在しない同質性を押し付けることによって個人の自由を奪っていくかということの警鐘にもなると思います。(注:念のため、繰り返しになりますが、これは決してそのような社会-個人間の関係の諸条件がその個人の視点を直接に規定していると言いたいわけではありません。そうではなく、一個人の視点はあくまでその人の社会との関係性によって生まれる経験を糧として培われるものであり、それらによって視点の取りうる可能性が規定されているわけです。)
さて、話が広がったのでもう少し視点を歴史学に戻しつつ—この「社会-個人の関係性の条件の複層性」に関連して、最後の論点として「社会-個人の関係性の条件の一つしての『時代性・現在性』」をあげたいと思います。私は大学2年生の時に取った科学哲学の授業で「パラダイム」という概念について学びました。これはもともと科学の発展に関連して考えられたもので、例えばニュートン力学など、科学理論の発展のおおもととなる考え方の土台のようなものです。科学哲学上でこの概念を理論化したトマス・クーンによれば、パラダイムとは時によって変わっていくものであり、その移り変わりこそがパラダイムシフトです。これを個人のユニークな視点の話と関連させて考えると、先ほどまで話していた「社会的条件による個人の持ちうる視点の範囲」に近いものがあると思います。このパラダイムは人文学の世界にも存在しています。ある論文が “paradigm-setting” という評価を受けているとしたら、それはその論文が後世の研究の方向性に大きな影響を与えたということです。そういうことはもともとわかってはいたのですが、卒論を書いていたあるとき、論を組み立てるための核として使っていた何冊かの学術書が全て基本的に一人の哲学者 (この場合ミシェル・フーコー) の影響を多大に受けて書かれたと気がついたとき、私はこれが現代の歴史学のパラダイムのうちにいるということか…、とある種呆然とした気持ちになりました。良くも悪くも我々は「巨人の肩の上に立つ」ことしかできない、この時代に生きるものとしてその時代のパラダイムのうちにたった見方でしか過去を見ることができないと悟ったからです。過去について考えることはあくまで現在という時間軸上の点から、現在というフィルターを通して過去を望遠することであり、たとえどんなにノスタルジアに浸って「古き良き時代」だか何かに戻った気分になりたくても、そんなことは不可能でその過去はあくまで「現在に存在する、現在から見た過去への視線」にしかならないのです。そんなこと当然と言えば当然です。それでもその、私の持ちうる視点の範囲が圧倒的に限定的であること、個人というものが、現在という時間のうちに、またさまざまな社会的条件の結び目の上に立った存在以上でもないし以下でもないという事実の圧倒的さに思い当たったとき、その超えることのできない限定的さ、思考とは時間と場所を自在に飛んでいけるものではないということに対する悲しさと共に、肝が座るような気持ちが生まれてきたのも事実です。それが動かせぬことであるなら、それでいい、それだから面白い。時と文化圏とそのほかいろいろな条件の結び目に堂々と立ち、そこから育つ自分の「視点」に矜持を持って過去を見ていこうではないか、という、歴史研究者を志すものとしての一種の覚悟が決まったとでも言うべきでしょうか。
以上が、卒論執筆という経験を通して留学全体を俯瞰したときに出てきた「わたしは、今に生きるわたしでしかありえないのだなあ」という、まあ当然と言えば当然のことへの多大なる感慨を、私に考えうる限りで少し解体してみたものです 。大学での学習・研究内容と留学生個人としての異文化の地での生活、その二つを私は引き離して語ることはできない一体のものとして捉えていますが、ここで述べたような思考の旅をするに至ったのも、留学経験なしではあり得なかったはずのことです。それを考えるとき、私は、語学力の向上・旅の思い出・人との出会いといったバラバラに得たもの以上の、けれどそれら全てが積み重なったところにあるものとしての人生の旅路のはかりしれぬ価値を感じ、6年前留学の決断をして本当に良かったと思うのです。
4. 個人的な話に戻し—おわりにそしてこれから
さて— (信じられないことにもうすぐ9000字です。大学のエッセイと違って文字数制限がないことはなんと素晴らしいのでしょう) ここからはもう少し軽く、私のこれからについて二言三言述べた上でレポートの締めとしたいと思います。きっと伝わったであろうとおり、私は私のやっている学問分野を心から愛していてここを離れることは想像ができないため、やはり将来は研究者を目指したいと思っています。(このほかに建築・芸術分野の本の翻訳や博物館のキュレーターにも興味がありますが、どちらも研究者になるレベルの専門性を持つことが必須もしくは大きなアドバンテージなので、今取るべき道としてはほぼ同じと考えていいでしょう。)そのために、アカデミアを目指す最低条件である修士号 (イギリスの場合最低一年間) と博士号 (イギリスの場合最低3年間) の取得をここ数年の目標としています。ただ、学部卒業後直接大学院に行く計画ではありません。予定では2年間のギャップイヤーを取ろうと考えています。 (周りのアカデミア志望には、前者も後者もどちらもいます。) まず消極的な、単純な理由を挙げると、自分が現在一番で志望しているのはイギリスの大学院で、そのための学費が今は足りないからです。ただ同時に、これは自分で納得して取った決断です。一応四年生の一学期中に応募できる奨学金は全額ではないにしろあったものの、卒論の方向性も決まってないうちにこれからの研究の方面をきちんと考えることはできない、寧ろのちのためにここで時間を取るべきだと考えました。実際これは大変良い決断だったと思います。これからの2年間、語学に勤しんだり、関連分野でボランティアあわよくば職務経験を積んだり、他分野の文献を読んだり、内容がぎっちり詰まったイギリスの大学・大学院にいる間にはできないような将来の研究生活に役立つスキルや知識を蓄えることはいくらでもできます。資金がない、というと同情されることもありますが、むしろこれまでなんの不自由もなく留学させてもらっていたことがあまりに特権的だったわけです。上に挙げた活動などと並行してもちろん資金を貯めるために(例え奨学金が手に入ったとしても全額ではない可能性が高いので)一旦アカデミアとは関係ない働き口を見つけるつもりですが、それは大学の外という新たな環境を経験できるということ、むしろさらに視点の可能性を広げられるようでわくわくするではありませんか。労働によって失われる時間はありますが、それによって得られるものは賃金だけでなく大学にこもっていてはわからない視点でしょう。こうして経験と知識を重ねリフレッシュした状態で、2年後に大学に戻ることを思うと今から楽しみです。卒論を書いたことによって新たな研究の方向性のアイデアも湧いてきたところです。大雑把な枠組みとしては、日本の近代の建築とデザインを、それをいかに日本という国で閉じたものではなく、他の文化との繋がり・交流と「世界の」建築・デザイン史のうちに語ることができるかを問うていきたいと思っています。もちろん先ほども言ったように、私は国家や民族への帰属意識で言っているわけではありません。自分の好きなことと自分ができること、そして学術の世界がいま求めていることが重なったところにある、未だ十分に語られていない過去を語っていくことが、私にとって世界全体の歴史理解を深める一助となるための最良の方法だと考えているからです。こうしてゆくゆくは、私の愛する視覚・物質文化、建築・デザイン・美術の歴史の世界で、「巨人」のほんの一部となれればそれ以上に望むことはありません。
とはいえ。アカデミアに生き貢献するのが私の一番の目標ではありますが、競争の激しい世界、それは夢でもあります。いつもフルタイムで一番やりたいことをやっているわけにはいかないことも多々あるでしょう。それでも常に大切にしていきたいのは、周りに流されず自分の決定に自信を持つということです。今思えば留学の決断をした6年前、当時の私は(受験勉強という形の勉強に疑問を持っていたことに加え)自分の趣味興味に関係なく、学校の成績ばかりで自分の評価やイメージが作られているような感覚に辟易し、そして成績によってこれからの道がある程度決められているような将来の展望に嫌気がさしていたように思います。そんな中留学は、私が本当にしたいと思ってした決断でした。そしてその決断に、一抹の後悔もありません。留学してからも、科目の決定、大学のコースの決定、大学の決定、コースの変更、日本で就職するかイギリスにいるか他の場所にいくかetc., たくさんの決断がありましたが、その時々で、前例がなかったときを含め (大変に優柔不断ながらも) 最終的に納得し自信を持った決断をしてきたつもりです。これからの長い人生も、留学を決めた時の自分を忘れず、自分が自分らしいと思える決断をしていきたいです。そうすればおのずから、自分らしい方法でこの世界に何らかのものを生み出し残す道が見つかるはずだと信じています。
最後の最後になりましたが、私が思いの向くままに生き学ぶことをあたたかく寛大にご支援くださった財団の皆さま、本当にありがとうございました。そして(物理的な距離の長短に関わらず)支えてくださった人々と、迎えてくれたバースとエディンバラの地、そして日々を彩ってくれたその気まぐれで美しい空模様にも感謝を申し上げ、レポートの結びといたします。
