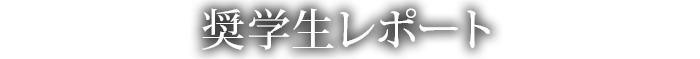
今年は、医学部のカリキュラムから1年間離れ、「インターカレーション」という制度を利用して、London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)で公衆衛生学の修士課程 (MSc Public Health)を履修しました。これまでとは全く異なる環境で過ごし、知的好奇心を大いに刺激された、とても充実した一年でした。今回はこの経験を “なぜこの選択に至ったか”、“修士のカリキュラム”、“修士論文について”、“その他取り組んでいたこと”の4つに分けてお伝えします。
“なぜこの選択に至ったか”
皆さんは、「公衆衛生」と聞いて、どのようなことを思い浮かべるでしょうか。私は以前、2年間ほど働いていたアルバイト先で、お客さんに「今は何を勉強しているの?」と聞かれ、「こうしゅうえいせいを勉強しています」と答えたところ、「それって歯学部の分野じゃないの?」と言われたことがあります。(どうやら「口臭衛生」と勘違いされたようです。)
もちろん、ここまで極端な誤解は珍しいかもしれませんが、「公衆衛生」という言葉だけでは、その範囲や内容を具体的にイメージできない方も多いかもしれません。実際、公衆衛生が扱う領域は非常に幅広く、新型コロナウイルスのパンデミック時における感染状況の把握やワクチン配布の計画といった疫学・感染症学・統計学から、医薬品や治療法の費用対効果を評価する医療経済学まで、多岐にわたります。
医学部を志したきっかけも、「恵まれない環境で暮らす人々を救いたい」という思いからであり、それを一番直接的に達成できるのは、医師として自分の手で人々の命を救うことではないかと考えたからでした。以前から、国境なき医師団などを通した、途上国医療への活動などには興味を持っていました。しかし、その道を進む方々と話したりする中で、このような地域が直面する貧困や格差、政治的な問題などといった構造的な課題がより一層見えてきて、それらを根本的に改善することに興味を持ち始めました。自分が医者として生涯に救える命の数は少ないですが、公衆衛生の観点からもっと広い視点で物事を見て、医療政策などに関わることができれば、より多くの人々に自分が出来得る最大限のインパクトを与えることができるのではと思いました。
このような経緯で、医学部1年生の頃から、大学外のプロジェクトに携わったり、論文の執筆をしたりと少しずつですが、公衆衛生について知見を深めることに努めてきました。幸いなことに、医学部在学中に修士を取得する機会に恵まれ、公衆衛生の基礎から学べるだけでなく、将来のキャリアを見つめ直す良いタイミングでもありました。そこで、この機会を活かして公衆衛生の修士課程に進むことを決断しました。
“修士のカリキュラム”
まず初めに、私が勉強していたMSc Public Healthには1年で終えるIntensiveと、2年間かけて行うPart time(ほとんどの学生が働きながら行う)、そしてすべてをオンラインで履修するオプションがあります。英国大学院は1年間で修了することが一般的なので、学ぶことが多くて大変と聞いていたものの、医学部の時ほど忙しくはないだろうという軽い気持ちでいました。しかし、後に真の“Intensive”の意味を知ることになります。というのも、医学部では病院実習などがあるものの、試験自体は年度末だったので、本格的な試験対策期間は比較的短いものでした。しかし、今回の修士課程は、3つのタームそれぞれでたくさんの単元を取り、全てに期末試験があったので、1年中課題に追われていました。
最初のタームでは、公衆衛生の基本となる疫学、統計学、社会調査をメインとした必修科目を学びました。ターム2とターム3はすべて選択科目となり、自分の興味に沿った分野を選択し、より深く学ぶことができました。私は医療経済に関心があったため、医療行為や医療政策の評価方法や、そこから経済の視点から分析する方法を学びました。
公衆衛生の課題というものは、自分の置かれた立場や、課題が存在する医療環境下によって正解が異なり、一つの解決策に絞れないことが多くあります。その中で、経済的な視点から考えることは、一定の指標に基づき数値化されたデータを活用できるため、より客観的な意思決定が可能になると感じました。
例えば、ある病気の治療にどの薬が一番良いかを考えるときに、治療行為全体にかかる「費用」と、得られる「治療効果」のバランスを考える、「費用対効果」という考え方があります。(これについては、もっと書きたいことはたくさんあるのですが、専門的になり過ぎてしまうのでまた違う機会に何かの形で書ければと思います)。この考え方は、限られた予算の中でどの医薬品などを選ぶかを考える上でとても大切です。日本の医療システムでは比較的新しい考え方ではあるものの、英国は費用対効果の情報を、医療における意思決定に活用している国として最も有名です。
英国には、1999年に設立されたNICE (The National Institute for Health and Care Excellence)と呼ばれる評価機関があります。そして、NHS (National Health Service)という税金で運営され、原則、医療費は無料の公的医療サービスがあります。NHSは、税収の伸び悩みや医療費の増大、高齢化による需要増加などによる財政難に直面していることもあり、限られた資源の中でどうやりくりしていくかが常に課題となっています。その中で、NICEは医薬品や医療機器などの費用対効果を評価する役割を担っていますが、費用対効果が良くないと判断された場合は、NHS(公的医療)での使用が推奨されなくなり、病院での使用は難しくなります。その際の評価基準は、明確な数値が決まっており、その基準値を超えたものは評価委員会での総合的評価を通さないと使うことができません。
一方で、日本では、「命に値段をつける」ということへの強い抵抗感があり、これが費用対効果評価の導入を難しくしているように見受けられます。「必要な医療は存在する限り受けられるべきである」という考え方が根付いており、経済的理由で治療選択肢を制限することに対する心理的な障壁は大きいと考えられます。しかし、日本も2019年から薬価制度に費用的効果評価を導入し始めました。ただし、英国のNICEのように「この治療は費用対効果が悪いので保険適用しない」という明確な線引きではなく、「費用対効果を考慮して薬価を調整する」という、より受け入れやすい形で導入されています。日本人の国民性を考えると、「治療の可否」ではなく「治療の優先順位付け」や「効率的な資源配分」という文脈で費用対効果を活用する方が現実的かもしれません。
こういったことを深く学ぶことができたのは、授業で扱われる具体的な例は英国のものが多かったものの、課題では、毎回自分の “the most familiar country”について書くことが多かったため、日本を題材にして取り組んでいたからです。その中で、英国の医療制度と比較しながら、日本の医療制度についてより深く知ることができました。そして、日本の医療制度が直面する様々な課題も見えてきました。また、世界各国から学びに来ていた学生がいたので、セミナーでのディスカッションを通して彼らの国の医療制度についても知ることができ、とても興味深い経験でした。
“修士論文について”
6月の初めに授業のある単元が終了してからは、本格的に修士論文に取り組み始めました。私は医療経済学への興味の延長として、指導教授が取り組んでいるエチオピアでの新生児栄養失調改善プログラムの経済的評価を行うことにしました。このプログラムは、授乳率向上を主軸としたランダム化比較試験(RCT)で、新生児の成長や認知発達などを「効果」の測定対象とし、保険システムにおけるコストと家庭負担コストを「費用」として、プログラム全体の費用対効果を評価するものでした。
3ヶ月弱という限られた時間で完成させなければならず、一時は本当に終わるのかという不安に駆られることもありました。しかし、スーパーバイザーから「すべてのことに手を出す必要はない。できる範囲のことを精一杯やり、できなかったことはディスカッションで言及すれば良い」とアドバイスを受けました。分析を完璧に仕上げることよりも、そこからどのような考察を導いたのか、どのような限界があるのか、今後どのような研究展開が可能なのかを詳しく述べることの方が重要だと教えられ、完璧主義な私は最初こそ戸惑いましたが、次第に気持ちが楽になりました。提出後には、論文としてのパブリケーションにも取り組む予定です。
“その他取り組んでいたこと”
今年は、例年にも増して様々なことにチャレンジできた年でした。中でも最大のイベントは、毎年5月にスイスのジュネーブで開催されるWorld Health Assembly (WHA)に、International Federation of Medical Students Associations (IFMSA; 国際医学生連盟)の代表のひとりとして参加したことです。
WHAは世界保健機関(WHO)の最高意思決定機関であり、加盟国・地域が参加する年次会議です。今年は第78回世界保健総会がジュネーブで開催され、世界130万人以上の医学生が加盟するIFMAの代表として参加する機会を得ました。
主な活動は、WHA会期中に開催される公式会議とは別のサイドイベントへの参加でした。私の担当分野である“Climate change and health” のイベントに参加し、知見を深めるとともに、様々なステークホルダーとの交流を図ることができました。
当初はIFMSAの存在すら知らずに応募した機会でしたが、この経験を通じて、世界中にグローバルヘルスに関心を持つ医学生が数多く存在することや、同世代の若者が様々な政策に積極的に関わっていることを知り、大きな刺激を受けました。普段の医学部では、公衆衛生は友人達にとってあまり興味深い分野と見なされがちですが、同じような関心を持つ同世代と交流できたことは非常に有意義でした(この経験についても、もっと書きたいことがあるので、別の機会に改めて書きたいと思います)。
その他にも、大学のバドミントンチームでのプレー、日本食レストランでのアルバイト、そしてランニングにハマってロンドンで開催された10kmのレースに参加するなど、忙しくもとっても充実した日々を送ることができました。
9月からは再び医学部に戻り、残り2年間の臨床実習が始まります。これまで以上に貪欲に新しいことにチャレンジしながらも、これまで取り組んできた活動もしっかりと継続し、さらなる成長を目指していきたいと思います。
