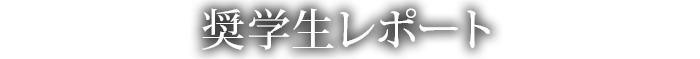
イギリス留学を通して私は自信がつき、物事を多角的に見られるようになったと思います。
私はもともと自己肯定感がとても低い人間で、優秀な兄を持っていたこともあり、常に比較対象となり劣等感に苛まれていました。日本にいた時は人の能力を判断する物として一番明確だったのが学校内での成績であり、周りが東京大学などのレベルの高い大学を目指す環境下では、成績の良し悪しが人の評価に直結する唯一の物差しでした。私は勉強がそもそもそれほど好きではなく、何より興味のないことを「将来のためになる」という大人からの言葉に従ってこなすのは苦痛でした。当然、成績も良くなかったため、学校に通っている間はテストのたびに自分が落ちこぼれであることを痛感し、勉強以外のことを始めるときでさえ「劣等生である」というレッテルに囚われ、前向きに取り組めていなかったと思います。
そのような中、私はTazaki財団のことを親を通じて知り、イギリスでは自身の好きな分野を高校のうちから学び、それを大学受験に活かせることを知って強く惹かれました。私はこの環境なら本領を発揮できると感じ、財団に出願するにあたり少しずつでもできることを増やしていこうというモチベーションが芽生え、初めて自主的に勉学に励むようになりました。特に英語は成長が最も可視化されやすかったため、一番力を入れて取り組みました。その結果、次第に成績は向上していきましたが、それでもなお目先の成績に囚われ続けていました。
いよいよ始まったイギリスでの留学生活。田崎さんからは「勉強だけでなくチャリティ精神やチームワークを学んでほしい」と言われていましたが、当初の私は新しい環境での生活や勉強についていけるかという不安ばかりで、文化交流をおろそかにしてしまいました。さらに自分の英語力に自信がなかったため、交流する人々は主に寮生のアジア人とTazaki生に限られていました。アジア人は文化的に日本と近しい点も多かったため安心感はありましたが、あまり新しい刺激を受けることはなく、話題の中心は直近のテストの感触などに偏っていました。
転機が訪れたのは、渡英して3か月ほど経った頃でした。その時ちょうど大学出願に必要なPredicted Gradeのための最初の試験が行われ、数学・物理・経済学それぞれ2つずつ試験を受けました。数学と物理はこれまで日本で学んできたこともあり難なくこなせましたが、経済学ではCという成績を取ってしまいました。(A-levelの成績はA*からEまでの6段階で、ある程度レベルの高い大学に行くためにはA*かAが必要) 周りのアジア人の反応としては慰めたり心配したりしてくれる事が多かったですが、イギリス人の反応は全く違いました。友人の一人はなぜ私が成績を心配しているのか全く理解できない様子で、問題点を洗い出すよりも「今できていること」に着目し、「それで十分良いじゃないか」というスタンスでした。その友人自身も同じくCを取っていましたが、成績が悪くても常にポジティブで、何より自分に自信を持っていました。
彼と私の違いは、彼が私生活において勉強以外にも熱心に取り組んでいることが多かった点です。例えばラグビーの練習に励んだり、学校の委員会活動に力を入れていたりして、彼には彼にしかできないことがたくさんありました。私が振り返って感じたのは、イギリスでは一人一人が自分の関心を模索する機会に恵まれており、周りと異なる興味を持った人が多いということです。だからこそ、日本のように同じ土俵で熾烈な競争を繰り広げるのではなく、自分にしかできないことを認識している人が多いのだと思いました。そしてそれがアイデンティティや自己肯定感に繋がり、自信に結びついていると感じました。
私はこの友人や他のイギリス人との交流を通じて、自分の得意なことに気づけるようになり、自分の良さや特性を自覚するようになりました。今までは興味のないことに全く手を出せない性格をネガティブに捉えていましたが、今では「興味のないことはできない代わりに、好きなことには時間を忘れるほど集中できる」という肯定的な見方に変わりました。このような考え方の変化は、自分自身に留まらず、今まで関わってきた人々や世の中で起こる出来事についても「こんな良い側面がある」と気づけるようになりました。
私はこのイギリス留学の二年間を通じて、より広い視野で物事を観察できるようになり、内面的に大きな成長を遂げられたと思います。このかけがえのない機会を与えてくださり、日頃から支えてくださった財団の皆さまをはじめ、友人、先生方、そして家族に心より感謝申し上げます。これから始まる大学生活に励み、将来は自分なりに経済学の発展に尽力していきたいです。
