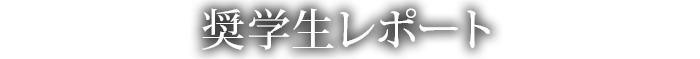
パブリックスクール生として書くこのレポートもいよいよこれが最後となってしまいました。最初は永遠に感じていた2年という期間も、今振り返ってみると刹那の間の出来事のように思われます。今回のレポートでは、これまでのレポート同様春、夏タームにあった出来事とその間に考えたことを分けて書いていこうと思います。
最後の2タームはまたもひたすらに大学受験のあれこれに苦悩するタームでした。春タームの3ヶ月間は大学からのOfferをひたすらに待つという期間で、いつ来るかもわからない合否発表に頭を悩ませながら過ごす日々でした。大学受験のためのテストや面接の後だったために比較的時間に余裕があり、今までやりたくてもあまりできていなかったトランペットやcodingなどに着手することができたのはよかったのですが、大学受験の結果のことや、のちに控えるAlevelの勉強のことが常に脳裏をよぎるために、その時やっていることになかなか身が入らない生活が続いていました。Easter holiday に入ってからはIeltsとAlevelの勉強に心身を注ぎました。自分が所属していたクラスは授業の進度が速く、Alevelの試験のための勉強もそれなりに進んでいたために、比較的余裕を持って試験に臨めるはずでしたが、高いgrade boundariesと失敗できないというプレッシャーから試験対策に全身を注いでいました。(オーバーワーク気味だった気がしますが、求められていた成績を取ることができたので結果オーライということにします。)Ieltsに関しては、Writingのスコアが思うように伸びず、過去に2度Offerで要求されていたスコアを逃していたため、十分に時間をかけて臨みました。結果としては必要なスコアをギリギリで取ることができたためよかったです。
ここからは、2年間の留学期間を経て、自分の中のどのような部分が変化し、どのような部分は変化しなかったのかについて、述べていこうと思います。
まず、個人的に最も変化したと思っている部分は知らない人と接することへの積極性です。私は留学前、1学年160人の中高一貫校に通っていまいした。この学校内では中学1年生の時に出会った仲間たちと6年間ともに時を過ごすため、気の合う仲間と出会い、ゆっくりと関係を深めていくことができるという利点がある一方、新しい人と出会うことが6年間ほとんどないため、大学に入ってからの人間関係に少々手こずる人が多いという難点があります。例に漏れず高校二年生の時の私は、その経験の浅さから新しい人と知り合い、仲を深めていくことに抵抗があり、それによって何人もの人と知り合う可能性を失ったと感じています。しかし、渡英して言葉もバックグラウンド
も違う人々との会話を強要され、その経験を積んでいくうちに新しい人と出会うことのへの恐怖心を好奇心が上回るようになり、人と出会うことに積極的になることができるようになりました。人を頼り、頼られるというのはこの社会で最も重要なスキルのうちの1つだと思うので、今後も人と関わることに積極的でいようと思います。
対照的に私のなかの根本的な考え方、というのはほとんど変わっていないような気がします。私は出国前の壮行会で運の重要性について話しましたが、帰国してからの帰国報告会でも「君の中のキーワードは『運』なんだね」と財団の方に言われてしまいました。日本に帰国して2年ぶりに話す旧友と話すときも、ほとんど変わっていなくて安心した、と言われることが多くありました。では、本当に全く変わっていないのかというとそうではない気がします。先ほどの「運」の話を例に挙げると、人生において運が重要であるという考え方自体は変わっていなのですが、自分の中の運の持つ「役割」は変化しています。過去には「運は機会をもたらすものである」と考えていましたが今ではそれよりも、「運は結果を返すものである」と考えています。つまり、幸運が降りかかってきたから人生が思うように進むのではなく、進みたい方向をしっかりと向いている人に幸運が降りかかると物事が思うように進む、ということです。比喩的になってしまいましたが、幸運が降りかかった時のリターンを出来るだけ大きくするための努力が大切だと今は考えています。思えば2年前、特にやりたいことが決まっていなくても、のちに選択肢を広く持つために、と学校の定期テストはなんやかんやで頑張っていた自分がいたから田崎財団に入ることができ、今の自分があるような気がします。これからも、すぐに今やっていることに意味を見出そうとせず、伏線回収のように、いつか今やっていることの意味が見えてくると信じて努力を怠らないようにしていきたいです。
最後になりましたが、2年間特に大きな問題もなくやっていけたのはずっと支えてくれた皆様のおかげだと思います。いつも影からこっそり見守ってくれる家族、くだらないことで笑い合える友達、大人の視点から生活をサポートしてくれた学校の先生方やホストファミリーの方々、そしてこの素晴らしい機会とご縁を提供してくださった田崎財団の皆様、本当にありがとうございます。これからも自分がいただいたものを誰かに還元できるよう精進していきますので、どうぞよろしくお願いします。
