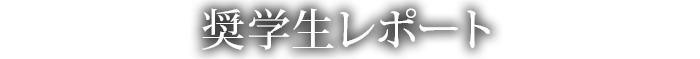
パブリックスクール生活の2年間が終わりました。
パブリックスクール最後のレポートでは、 2年間の大学出願プロセスについて、自分の視点からまとめます。一部の特殊な用語についてはレポートの末尾に説明をつけましたので、ご確認ください。
まずは、Aレベルの科目選択から始まりました。専攻が定まっておらず、過去にコンピュータサイエンスをAレベルとして取った先輩がいないと聞いていたため、初めは数学、発展数学、物理、化学の4科目を選択しました。しかし、2~3ヶ月ほどAレベルの化学を受講する中で、単調な計算と暗記を繰り返す作業に興味を持てなくなっていきました。ちょうどこの時期コンピュータサイエンスの専攻を決断したため、先生に相談してAレベルのコンピュータサイエンスの体験受講をしました。この時化学よりは興味が持てそうだと確信し、変更に踏み切りました。しかし変更前の化学の成績はトップだったため、教務部長兼化学教師の先生の腰は重く、「コンピュータサイエンスでA*を取れると誓えるならいいよ」としぶしぶ言われました。その時ははったりで取れると言い切りましたが、内心取れるかはかなり不安でした。キャッチアップも必要で、その直後の冬休みは勉強漬けとなりました。
専攻の選択にあたっては、自分の興味や没頭できるものが何か、大学での日々のスケジュールを楽しみこなせるか、自分の好奇心旺盛で何にでも手を出したがる性質とマッチしているのは何かなどと考え続けていました。当時はコンピュータサイエンス学部の人気の高さは考慮しておらず、この後少しずつその競争率の高さに驚かされることとなります。
Aレベルの科目選択については専攻に準じた科目を選ぶのが通常ですが、ここでは補足として先に知っておきたかったと思う別の視点も紹介します。
まず1つ目は、良い成績をどの程度取れる可能性があるかです。科目によってそれぞれのグレードを獲得する生徒の割合が異なります。例えば、A*を獲得した生徒の割合は、2023年度は
Maths: 16.9% Further Maths: 28.7% Chemistry: 9.8%
Physics: 11.3% Computer Science: 5.8%
でした。受験生の人数や、その科目がどの専攻に必要なのかにより、受験層の質が異なるため、この数値の意味合いも変わります(Further Mathsはそもそも選択している層が優秀なのでA*が多い、など)。また、母語が日本語であるという点も踏まえると、エッセイが多い科目は相対的により難しくなると思います。
2つ目は、大学の学部の要求する科目です。コンピュータサイエンス学部に限った話では、ケンブリッジは2024年度からFurther Mathsの受講を必須としました(急な変更だったため、選択していない生徒への対応措置はありました)。一方、コンピュータサイエンスを必須にしているところは知る限りありません。ならコンピュータサイエンスを取らなくてもいいかと言うと、学校が科目として提供している場合はなぜ選択しなかったのか問われる可能性があります。
そもそもコンピュータサイエンスが必須でない理由は、Aレベル科目として提供できない学校が多いからだと思います。またもっとシンプルに、コンピュータサイエンスを選択したことで、授業で習う考え方が自然に面接対策になったり、プロジェクトをパーソナルステートメントに書けたり、知識体系が大学でも役に立ったりといったメリットがあります。
これら2つの点を科目選択していた当時知らず、自分はただやりたい科目を取りました。それももちろん良いですが、心配に思う方は上記を踏まえた上で作戦を立てると、どの受験ステージで一番努力をすることになるかを多少調整できるかもしれません。
次に、大学選びをしました。大学ごとのコンピュータサイエンス学部のAレベルの条件の具体例は末尾に載せましたが (※1) 、自分が行きたいと思える大学は、A*AA ~ A*A*Aくらいを求められました。ただ、オンラインで調べたりオープンデイ(オープンキャンパス)を回ったりする中で、これはあくまで入学条件であり、オファーの条件ではないということがわかってきました。例えば出願者のうちオファーをもらう割合は、
Cambridge: 9.3%、Oxford: 6.8%、Imperial: 16%、UCL: 7.6%
などとなっています。そして、コンピュータサイエンス人気は、この数字以上に、出願者のレベルが高く、多くの人が3A*や4A*のpredicted gradesを提出する点でした。ケンブリッジは、出願者の割合として、ざっと半分くらいはStraight A*を取っています (※2)。大学側としてもpredicted gradesが高い人を評価しているようで(というよりも低い人を切り捨て)、例えばバース大学のオープンデイに行った際は、オファーを出すか決めるのには基本グレードしか見ないからpredicted gradesで3A*を取ってね、と言われました。さらには4A*でもUCLやBristol、Durhamからオファーすらもらえなかったケース(主に学費が低いイギリス市民ですが)を聞いて、Straight A*は最低ラインなのかと驚き、同時に負けず嫌いの血が騒ぎました。
しっかり準備をして臨んだYear 12 の模擬試験では4A*のpredicted grades、それに加えて受けたAレベル Japanese の本試験でもA*を獲得することができたため、希望の大学に安心して出願できました。
そして一番受験らしいイベントとも言えるのが、パーソナルステートメントの執筆です。パーソナルステートメントを充実させるために、日本にいた時以上に、Year 12は科目に特化したことに挑戦しました。それまでは物理や建築など趣味のオンラインコースを受講し楽しんでいることも多かったのですが、機械学習や数学によりフォーカスするようになりました。パーソナルステートメントの執筆は、これらの活動を自分の軸が浮かび上がるような形にするパズルのようなもので、何十回もフィードバックをもらい訂正を繰り返しました。先輩方から早めに始めた方がいいと聞いていたため、夏休み中に終わらせてしまおうと意気込み、夏休み後半はずっと執筆と向き合っていました。そしてついに財団支援のチューターにこれでいいよ、と言ってもらえるまで仕上げ、夏休み明けに意気揚々と学校のチューターに提出すると、「冒頭部分の、コンピュータサイエンスをやりたい理由が共感できないから書き直しなさい」と理不尽な拒否権を喰らいました(学校のチューターから許可が出るまで、出願をさせてもらえません)。これを3~4回は繰り返しましたが、このフィードバックはパーソナルステートメントの向上には特に役に立たず、無限の内省は精神的に酷でした。しかし人間面白いもので、何度も「本当にそれが自分の本質なのか?」と問い続けると自分の思考の癖や、幼少期の経験や読んだ漫画(「風雲児たち」など)が自分の人生の目標に意外な影響を与えているなど関係のない新たな発見もあり、自分を再認識する面白い時間となりました。最終的にパーソナルステートメントは留学後の活動(職業体験、オンラインコース、学問オリンピックなど)についてがほとんどを占め、渡英前に行った関連した活動(サマーコース、学問オリンピック)も一部含めました。
さて、過去の生徒のパーソナルステートメントを読む中で、コンピュータサイエンスは物理や経済など他の理系の科目に比べても性質が明らかに違うように感じました。何歳からでもプログラミングを使ったプロジェクトはできるのに対し、物理や経済はしっかり基礎を学ばないと自由度と新規性のあるプロジェクトは難しいです。コンピュータサイエンス志望にはいわゆるプログラミングオタクが山ほどいて、どんなアプリやコードを書いたか、ということをみんな書き、それを実際にアドミッションは評価しているのではないかと推測しています。当然、「数独を解くコードを書いた」というのと「2年間かけて企業と協力しゲーム開発をした」などプロジェクト間の質は大きく異なり、どの程度「考えてきたのか」が自然と表出します。他の物理や化学などの科学は、本や雑誌について書くなどしますが、プロジェクトという目に見える「活動記録」が存在する情報の分野で本の批評が重視されるようには思えません。プロジェクト以外では、情報オリンピックや、数学オリンピックなどで良い成績を取るのも評価されていそうです。数学力を大学が高く評価しているというのはよく聞く話です。幼少期からのプログラマーではない自分は、脳科学や数学との学際性を主張しながら組み立てましたが、どう評価されたかは不明です。
パーソナルステートメントを提出した後には、アドミッションテストを迎えました。コンピュータサイエンス学部では、基本的に数学の試験を受けることになります。ケンブリッジやインペリアルなどに使われたのがTMUAという試験で、IELTSに似て9.0上限のグレード評価が行われます。選択肢問題で、数学の小問を短時間でたくさん解くというものでした。対策をした印象としては、足切りに使われるのかなというようなレベル感でしたが、本番は形式が前年から変わっていたこともあり難しく感じました。一方UCLでは2024年度はSTATという試験が使われました。これはオーストラリアで使われている試験で、数学と英語読解の選択肢問題でした。興味のある方にはぜひサンプルテストを解いてもらいたいのですが、STATでは風刺画の皮肉についての問題などもあり、英語読解については対策のしようがありませんでした。何故コンピュータサイエンス学部のためにこれを解かされたのかはいまだに疑問です。
自分の場合はどちらの試験もとても良い成績が返ってきたため、それが面接~オファーに最も貢献したかと思います。
オックスブリッジはどの学部でも必ずインタビューがあり、predicted grades、パーソナルステートメント、アドミッションテストを踏まえてインタビューに呼ばれるかが決まります。インタビューは各生徒2, 3回、1回30〜40分が平均だと思います。その内容としては、コンピュータサイエンス学部の場合10分程度パーソナルステートメントについて話し、そのあとの残りの時間で数学の問題を解いていく、というのが通例と聞いていました。しかし、いざ蓋を開けてみるとパーソナルステートメントには一切言及されず、面接のために作られたウェブサイトで、面接官の前でリアルタイムのプログラミングをするよう言われました。2回ともアセンブリ言語とPython類似言語をそれぞれ用いた比較的シンプルな問題で、数学的思考力を30分間ひたすらに観察されました。パーソナルステートメント関連で議論をしたい気持ちもあったので残念でしたが、大学が求めている生徒を、様々なバイアスを軽減し見分けるための緻密さが感じられました。プログラミングが終わり、「最後に『質問はありますか?』と聞かれる」と予習していたため質問内容を思い出していると、気づいたら先生が退出しており、狐につままれたような気分になりました。
これらを経て、少しずつオファーが届きはじめました。ブリストル、ダラム、UCLからは予想より条件の低いオファーが届きました(Japaneseを条件を満たすために使うことを認めてもらえたため)。そしてケンブリッジのオファーが届いた時は非常に嬉しかったのですが、よく見ると条件が「発展数学、物理、コンピュータサイエンスでそれぞれA*」という類をみない難易度でした。周りの友達が大声で祝福してくれているからこそ先が思いやられ、喜ぶにも喜びきれませんでした。
最後にAレベル試験本番を迎えました。数学、発展数学は無難に終え、物理はエッセイを1問書き忘れるという事故があったものの、2年間の練習問題の甲斐あって良い手応えとなりました。コンピュータサイエンスは、例年以上にエッセイが多いと感じました。エッセイは、基礎知識を入れた上でそれを文脈に沿って必要な知識のみに取捨選択し、それらの要素を上手くつなげたうえで最後に論点をまとめる結論を書く、という他の設問より難しいものになっています。定義やアルゴリズムの問題は暗記してしまえば満点近く取れますが、エッセイは時間制限も相まって難しく、ここでいかに綺麗に内容の濃い物が書けるかがA*とAを分けるだろうと心していました。本番は何とか書き切ることができ、A*とAで五分五分だろうという所感で終わりました。Aレベルの結果までは2ヶ月ほどあり、終わった直後はその日が非常に遠く感じましたが、趣味の旅行や卓球をしていたら意外とあっという間でした。発表日に4A*を確認できた時は喜びと安堵が入り混じり、受験を始めてから初めて、落ち着いて達成感を味わうことができました。
Aレベル全体としては、2年間と長い割に内容にあまり面白さがなく、先生も発展的な話をしてくれないため、集中力が多々切れる時期がありました。それでも授業だけはちゃんと集中して受けたため知識や理解力は確実に身についていったように思います。
パブリックスクールそして受験をこうして振り返るのももう無いだろうと思うと、清々しい気持ちになります。丁寧にやり切れたことを自信に、前を向いて生きたいと思います。
受験の話はここまでとし、最後にこの2年間を大まかに振り返ります。まず、本をたくさん読めたのは非常に良かったなと思います。日々に忙殺されかける中、純粋な好奇心を保っていられたのはひとえに偉大な先人たちゆえです。特に記憶に残っているのは Elon Musk (Walter Isaacson) と Being you (Anil Seth) です。どちらも自分の中の常識を崩してくれました。また他に、学校内外で様々な人に出会うなかで、価値観の相違について考えさせられました。特にイギリスは社交の経験値が信頼度につながる部分が大きいと感じ、その価値観と自分の論理至上主義的な価値観との折り合いを上手くつけるよう心掛けました。価値観に正解があるのかは不明ですが、自分の中でしっくりくる生き方や倫理観をこれからも常に探求し続けたいと思います。
最後になりますが、Tazakiの先輩方の皆様、8期生のみんなやHall HouseのKさん、貴重な話や興味深い話はもちろん、たわいのない話にも付き合ってくださりありがとうございました。7期生の同期とKingswoodの同期のみんな、いつも刺激をくれてありがとう。特に部屋が2年間隣だったSさんには、精神的な面で多く支えてもらい、感謝してもしきれません。そしていつもご支援いただいている田崎さんはじめ財団の皆様、いつも応援してくれている家族のみんな、改めて本当にありがとうございます。
今後とも自分の道を拓き続けます。
(※1) 大学ごとのコンピュータサイエンス学部のAレベルの条件 (2024/2025)
Imperial: A*A*A* or A*A*AA
Edinburgh: A*A*A*
Cambridge, UCL, Warwick, Manchester, KCL, Bath: A*A*A
Oxford, Birmingham, Bristol, Durham: A*AA
St. Andrews, Queen Mary: AAA
(※2) FOI request
https://www.whatdotheyknow.com/request/computer_science_admissions_stat_68
(※3) 用語説明
オファー: 条件付き合格。選考後、大学がその生徒を受け入れる場合、生徒に送られる。通常はAレベル本試験で一定以上の成績を取らないとその大学に入学できず、その成績の条件がこのオファーに書かれている。
Predicted grades: Year 12の年度末にAレベル模擬試験があり、その結果の成績。学校が独自にテストを作り、その結果などからその生徒が本試験で取れそうな成績を算出する。出願するときに大学に提出され、オファーを出すかの判断材料の一つとなる。
Year 12: 渡英1年目の学年。Aレベル試験のための勉強が始まる学年。
Year 13: 渡英2年目の学年。年度末にAレベル本試験がある。
パーソナルステートメント: 大学に提出するエッセイ。自分がなぜその学部に入りたいか、どんな活動をしてきたかを書く。原則、すべての大学に同じエッセイを提出する。
アドミッションテスト: 一部の大学の学部に出願したときに受ける必要があるテストの総称。大学がオファーを出すかの判断材料の一つとなる。
IELTS: 英語の能力試験。イギリスの大学に入学するために、留学生はIELTSでの英語能力の証明が求められる場合がある。
Hall House: 寮の名前。Kingswoodの男子寮の一つ。
