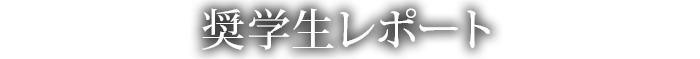
長いようで短かったChrist’s Hospitalでの2年間を終え、日本に帰国しました。今は日本での学友たちと再会し、お互いの近況を伝え合うなどして留学の疲れを癒し、あとひと月程で始まる大学に備えています。このレポートでは、これまでのPublic schoolでの生活を総括するものとして、近況報告、2年間で得たもの、大学入試とこれからの抱負の3つの軸に分けて話していこうと思います。
まずは近況報告からですが、つい先日A-levelのResult Dayがあり、無事オファーの条件を満たし第一志望であるOxfordに合格することができました。Pembrokeというカレッジで工学(Biomedical Engineering)を勉強する予定なのですが、どんなことを学ぶのか、どのような大学生活になっていくのか今から楽しみで仕方がありません。これもすべて、日常生活からサマースクールなどのアクティビティまで様々な支援をしてくださった財団の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。また、生活面、学業面に際して、日々の交流を通じて刺激を与え続けてくれたCHでの同級生や財団の同期の皆にも感謝したいです。これからは活躍の舞台が更に広く分かれることになりますが、皆がそれぞれの分野で輝く様子を見るのを楽しみにしています。
学校での生活についても触れると、最後の2タームの大部分を占めた試験勉強においては、前回のレポートでも触れたMellstrom centre(自習室)と図書館が自分にとって最適な勉強場所となり、常に高いレベルの集中力を維持する大きな助けになってくれました。毎日授業が終わったら直ぐにMellstromに向かい、特に試験期間やその直前は自室にいるよりも長い時間を自習室で過ごしていましたが、ほとんどの利用者が全く喋らずにお互いの学習環境を尊重し合っているのでモチベーションを保つ助けにもなりました。またCHは広大な敷地の中に緑豊かな散歩道が多くあり、休憩として学校を歩き回るのが趣味にもなっていました。様々な面で本当に恵まれた環境に身を置いていたと、卒業した今だからこそより強く実感します。
A-level試験が近づくにつれ時間は矢のように流れ、ちょうど1カ月続いた試験期間も一瞬のように感じました。学校中で最後の試験となるFurther mathsのDecision1を受けていたので、周りが次々と試験から解放されていく中最後まで気を引き締める必要はありましたが、これも同じ科目を選択している友人の存在に助けられ試験が終わった際には達成感を全員で共有しました。また新しいことを習うわけでもなく毎日復習だけを続けることに当時は退屈さも感じていましたが、振り返るとその努力が順当に結果につながっていると思え、報われたように感じています。
すべての試験が終了してからはSpeech dayやGrecians ball, Leaver’s serviceなど様々なイベントがありました。Speech dayでは計3つの賞をいただき、それぞれ直接ロンドン市長代理に表彰していただいたのですが、その際写真撮影も行われるため何度も登壇しては市長と握手し、カメラの方を向くのに少し気まずさすら覚えましたが、もちろん嬉しさもあり特にいただいた賞のうち2つはAcademic関連(Fmaths, Chemistry)だったので誇らしく思いました。他にも市長がChapelに入場するときのPhalanxを担当させていただくなど様々な経験をさせていただき、途中入学である自分に帰属意識を与えてくれたCHには深く感謝しています。
次に、自分が2年間で手に入れたものについて述べようと思います。とくに大切にするようになったのは、挑戦を楽しむ心と、コミュニティへ還元する意識の2つです。このレポートを書くにあたって昔自分が書いた報告書にも目を通したのですが、渡英当初はやはり肩に力が入っており、留学生活から何かを得ようとするのに必死で足元を掬われることも多かったと記憶しています。しかし、結果論かもしれませんが、今過去を顧みると自分の中でその努力は必要不可欠だったと思っています。というのも、留学前の自分は極めて保守的で、安定を好み流れに身を任せるきらいがありました。勉強も周りに負けたくないから、などの理由でやっていたに過ぎず、高尚な理由もなくどちらかといえば惰性で続けていたに近い状況でした。ただしその中でTazaki財団に出会い、自分がやりたいこと、なりたいものが明確になるにつれて少し身の丈以上の努力や意識改革が必要になっていき、それに駆られる形で新しいものに挑戦する機会が増えていきました。特に渡英してからすぐは無理をしてでも様々なアクティビティに身を投じていたため、先にも触れたようにそれで自分の首を絞めることもありつつ、自分の世界を広げる喜びを学ぶことができました。あの時に自分の殻に閉じこもる選択をしていたら、今の友人たちとの関係や新しく得た趣味、知見など、それら全てを逃すことになっていたかもしれません。また知<好<楽というのは孔子の時代から言われていますが、渡英後の背伸びは挑戦の大切さを知り、その結果を好み、挑戦という行為そのものを楽しむように至るまでの重要な基盤になってくれたと思います。
コミュニティへの還元に関しては特に最近意識するようになったのですが、今まで身をおいてきた様々な環境において、自分の存在は多かれ少なかれ周りに影響を与えてきたはずです。これは別に自分の影響力を過大評価するものではなく、多数の人間が相互に干渉し合ってできる社会の性質からとなっています。しかし、今まで自分は能力不足から周りへの恩返しを始めるにはまだ早いと思い込んでおり、環境から何かを得ようとするばかりでした。それに気付いたのはついこの間出身の小学校、中高を訪ねた際に後輩に対して言葉を残すように頼まれたときです。まだまだ未熟な自分でも既に後進を手助けする事ができるのだと思わせてくれるとともに、多感で影響を受けやすい時期の後輩たちを相手にして一つ一つの発言に責任感を感じました。所属するコミュニティで良い市民であろうとするだけでなく、組織、ひいては社会全体を自発的に導き、形取っていくことの大切さを忘れずに意識し続けたいと思います
最後に大学入試の経験を共有すると、自分はOxford, ICL, UCL, KCL, SouthamptonのBiomedical Engineeringにアプライしました。渡英時から常にICLが第一志望で、当初はOxfordに出願するつもりも無かったのですが、出願の枠が余っていたこと、Summer schoolで一ヶ月宿泊したPembroke collegeを気に入っていたこと、9月の中旬にはPersonal statementがほぼ完成していた事などを理由にEarly entryをすることに決めました。ICLとOxfordのどちらに行くかは本当に最後まで迷っていたのですが、自分で調べるだけでなく周りにも意見を仰ぎ、講義やTutorial,宿泊施設などを総合的に判断して自分にはOxfordがより適しているという結論に至りました。入試のプロセスに関しては大学や学部によって大きく異なるものではありますが、自分の場合はPATとInterviewの2本柱となっており、面接はPersonal statementについて少しだけ触れられた後は確率や微分方程式、放射熱など、数学や物理の問題を試験官に説明しながら解く形になっており、自分の思考プロセスを逐一言語化するのは少し曲のある作業となりますが、問題は全て応用的で現実世界での例え話のように出題されるため慣れるとその難易度の高さも楽しめると思います。PATなどの外部試験はA-levelと形式が大きく異なることが多いため、それ専用の対策をすることが推奨されるとともに、場合によっては複数受験しないといけない可能性もあるため前もって大学の出している情報を確認しなるべく早く準備を始めると良いと思います。
これからは大学が始まり、より一層自律的な学習習慣や挑戦心が必要とされてくると思います。引き続き新しいものを恐れず、最高の環境で人脈や経験、学びを最大限得ることができるよう努力したいと思います。自分自身の軸をぶらすことなくアップデートし、社会に飛び立つ前の最後のステップとして、実りある大学生活を送れるよう精進します。これからもよろしくお願いします。
