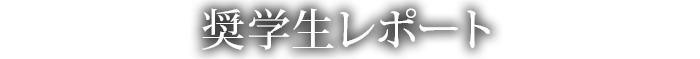
羽田からヒースロー空港を目指す飛行機に乗りながら、お月見をしているところです。まんまるに照り光る満月の下には、何層もの色がぼやけながら塗り重なっていて、そのまた下にある北極の白が、ところどころ朝日を拝んで桃色に染まっています。誰か雪の上を歩いているかな、なんて無邪気に思って目を凝らしていましたが、一万メートル上空を飛翔していることに気づき、自分はなんと小さい存在なのかと改めて感じておりました。細い川があると思ったのですが、おそらくとてつもなく雄大な氷河谷だったのでしょう。
さて、七月にKingswood Schoolを堂々と卒業してきた私ですが、この二年間、新しいことにはなんでも挑戦し、与えられた機会をもう二度と無駄にはしないと腹を括って生きてきました。スポーツから音楽、美術、演劇、勉学、クラブ、ボランティア、そして生徒会活動など多岐に渡った分野に足を踏み出すことで、段々と交友関係、信頼関係も広がっていったと感じています。私のその、多様な人と繋がろうと努めた姿勢を多くの先生方が見守っていてくださり、卒業イベントでは大役を任されたり賞をいただいたりしました。
教会でのLeavers’ Serviceにてハウス代表として朗読を指名され、この場においても、更なる新たな出会いの輪が広がりました。同級の卒業生と親御さん、先生方が、私が一人自室で何度も練習した暗唱を届けるのを、心を込めて聞いてくれたと思います。朗読文の中でお気に入りの言葉はMay we be a channel of your peace, breaking down walls of prejudiceです。これはまさに、自分の二年間の生き様を写した表現ではないか。つまり、日本からやってきた留学生が、がむしゃらになって何事にも前向きな態度で取り組んだことは、周りの人達への刺激になったのではないでしょうか。見た目や言語の違いはもとより、新しいことに対する恥じらいの気持ちや、責任を負うことへの抵抗感などを、少しでも打ち崩すひびを入れられたのではと思っています。式典の後、全身に語りかけてくれたみたい、などとお褒めの言葉をいただいたことを今後の成長へと繋げます。
いわゆる卒業式であるPrize Givingでは、Contribution to SportsとCommunity Spiritのダブル受賞に与りました。Bath のThe Forumを私一人の独壇場として二連続で壇上を悠々と闊歩し、校長先生の分厚くて力強い手を握れたこと、そして全校生徒の拍手をさざなみのように全身で受け止められたことには、相好が崩れっぱなしでした。
けれども、やはりどんな賞や肩書きや拍手よりも一番温もりのある思い出をつくってくれたのは、寮のメイトロンさんたちや、料理人の方々でした。あなたが卒業したら寂しくなるわとか、そのトロフィーと盾はなあにと、個人的に話しかけてくださったことは生涯忘れません。普段あまり表舞台に立たない方々に、日々挨拶や感謝の気持ちを伝えることの大切さに徐々に気づけた私は、彼らにとって自分から声をかけたい存在にまでなれたのかと思うと、喜びが弾けます。渡英したての頃は拙い英語力もあり自分から人に話しかけづらく、しかしそんなとき、気さくに話しかけてくれ、ゆっくりと私の話に熱心に耳を貸してくれた友達や先生、ホストファミリーがいました。この経験があったからこそ、私はより広い視野を持って、多様なお役目につく職員の方々や街の人に自分から声をかけられるようになれたのでしょう。まるで娘と別れるみたいだわ、と涙で私の肩を濡らしてくれたメイトロンさんをはじめ、本当にお世話になった人達の元に、また必ず戻り、大量のお土産話を聞かせたいです。
帰国した後、二年ぶりに母校へご挨拶に伺いましたが、初等科、中等科の先生方の全くお変わりのない姿や、どんどん弾んでいく話し口調、大変懐かしい思い出が多く甦ってきました。大人になったなあとか、そんなに色々挑戦する人じゃなかったわよね、などと先生が言ってくださいました。この学び舎で体得した心構えや能力を基盤として、成長した姿をお見せでき、ほんの少しは先生に恩返しができたでしょうか。
どんなに遠くへ行ったとしても、帰る所、そして恩師がいるということは、何よりも心の励ましになります。
日本へ帰る飛行機の中ではふと、はたしてこの二年間がいっときの夢になってしまうのではないかと、少し肝を冷やしていました。このまま日本で夏を過ごせば、留学前の自分と何一つ変わっていない自分になってしまうのではないかと。けれどそのときにまた、これから先、自分の行動、思想、姿勢の一つ一つに、英国でご縁があった皆を思い出していこう、と決意しました。例えば地理教諭の、何事にもユーモア交じりの前向きな姿勢で周囲を巻き込みながら真摯に参加していく背中や、クラスも違い、当初は自分からはあまり話しかけてこなかった同級生に、長年の友達かのような口調で話しかけてくれた友人のその目。その時々で、見習うべきだな、助けてもらったな、と受け取った人柄や姿勢。それらを真似していき、いつか自分のものとすることこそが、いつでも見守ってくださる皆へ何かを与えられると考えます。一つずつ経験や考えを重ね、常に相手から学ぶ姿勢を持ち、九月から始まるエディンバラでの大学生活でも一所懸命の精神で頑張ります。
二年ぶりの日本。暑さに全てが焼け焦げてしまうのではという危惧はついに消えませんでしたが、実に数々の地へ旅行しました。英国滞在中、日本文化について聞かれ曖昧な答えを返したり、友達の方が私より日本各地へ行った経験が多かったりと、日本で生きてきた身として恥ずかしく悔しい思いをしていたので、この度は群馬、兵庫、大阪、広島、伊勢へと夏を満喫して参りました。
阪神甲子園球場では高校球児の熱い暑い試合を観戦しました。テレビでは届かぬブラスバンドの重低音に、それに重なり響き飛ぶ野球部員のメガフォンから投げられた大声援。ついに躍動する球児達が自分より年下になったのかと思い、おばあちゃんになっても再びこの青空の下へ戻って来るぞと誓う私は、高校野球好きの想いは流れる時間の中で絶えることはありません。
テレビでは個々の顔がよく見えますけれど、やはり自分だって一緒に参加したいのです。ここで指笛でも吹けばそれはたちまち選手、観客に伝わりますし、拍手をしても、響き渡る歓声に加勢できます。一球一打に一音、そして一呼吸にどよめく場で、大海原の波となった声援は鼓動をつたって自分の一部となります。どうして好きかと問われたなら、理由もなしに好きなのだと。胸を張って言い続けられるそんな好きなことは、何があってもやり続けたいです。
広島にて。原爆ドームと戦争。この二つの単語を安易に結びつけてはいけないと、スマホ片手にベルトコンベアーに乗っているかのように素通りする人達を見て、感じました。
そこに生きた人、今生きる人を学ばなければ、積み重ねられた人類の記憶は風化していってしまうでしょう。
広島を訪れるにあたって、はだしのゲンを読みました。中岡元という一人の人生が描き綴られています。マンガには文と共に絵があります。言葉だけでは表し尽くせぬ顔の細かな表情に、文字を使った生々しいリズムがあります。マンガを読むとまるで、自分が主人公と一緒の体験をしているよう。相手と、ときを共有するからこそ、より自身の思考も深掘りできるのだと思います。
学校生活においても、その人自身を学ぶこと、要するにこの人物が人生を通して育んできた人となりを学ぶことの毎日でした。と言いますのは、例えば私が同じ話をしたとき、各々驚いてくれる箇所は異なり返答も違います。そこが面白いのであって、その相手とでしか紡げない会話が、我々の価値観にときに強く訴えかけるのでしょう。
どんな数学の内容よりも体にすっと入ってきたのは、先生の学生時代の旅のお話。生まれたての息子の写真を愛おしそうに、誇るように見せにきて下さる先生の優しい目尻。こういったものが私に、他人と経験を共有できることが、いかに大きな素直な喜びをもたらせてくれるのかを教えてくれました。
マンガで話を繋ぎますと、手塚治虫さんは、絵が上手くなりたいのならまず電車かバスに乗って、人を心でスケッチすることを言及していました。まるで探偵のようですが、まず注意を払ってみると、人によって顔の動かし方が違うなあなど、結構興味深いことを知ります。何も人でなくとも、建物だって構造を目で追っているといつの間にか顎が真上を向いている、なんてすぐ没頭してしまいます。かのシャーロックホームズの生みの親アーサー・コナン・ドイルが暮らしたエディンバラの地で建築、美術、歴史に、今生きる様々な人々に触れられる幸運をしみじみと感じています。
六月末に終えたA-level試験後、ロンドンのホストファミリー宅で一週間過ごしました。この旅は試験のご褒美でありますが、オペラ鑑賞、美術館や博物館に行ったり、広大な公園や市内の展望台で鉛筆を走らせ気ままにスケッチをしたりしていました。絵を描くと記憶が繊細に色とりどりの映像として残ります。絵を描いているよ、と囁く声や、綺麗だねと言ってくれた顔もよく覚えていますし、けれども一番いいのは、絵は人に見せられることでしょうか。記憶が私に歩調を合わせて一緒に旅をしてくれて、見せたい相手に思い出の宅配便を送ることができます。
絵の他にも、例えば受け継がれるお作法は、時空を超えて、人々の想いの共有を可能にさせてくれるでしょう。先日、千玄室さんが逝去されましたが、茶道は一期一会の機会をつくり人と人とを結ぶ文化だと思います。茶道を習う父と共に、夏の間だけお稽古へ行きましたが、多くの貴重な姿勢や考え方を教わりました。例えば、お道具を帛紗で清めるのは、心を清めるのと同じことである。お客様としてお道具の拝見をするとき、作った人に想いを馳せて感じ取りながら鑑賞する。悟りを開いた心境と、お茶を立てる心境、そしてお茶をいただく心境は同じなのである。などです。茶室に、千玄室先生が書いた「千里同風」の掛け軸、花入れに見立てられた経筒の中に凛と、白と黄のお花が生きる空間がつくられ、一堂に会した人々が一服のお茶を飲む。言葉にしてしまえばなんてことはないですが、こういった精神は世代を超えて受け継がれる大事な文化となっています。千里をも、千年をも越えて吹く風があるように、お茶やマンガなどの、大勢が日常で触れられる文化を、自分の手で新たに創造できたならば、どんなにか光栄でしょうか。万人の手に触れられて育つ文化は、幾重にも増して数え切れない、彩り豊かな体験を語り継ぐことができるでしょう。
最後になりますが、二年間の高校生活を手厚く支えてくださった財団の皆様、これからも初心を忘れずに、全ての人とのご縁を大切にして大学でも毎日精進して参ります。
二年ぶりに再会した友人達、皆がそれぞれの道を進んでいるけれども、同じ時間を過ごせればいつだって、いつもの楽しい雰囲気がたちまち滲み出すから、迷うことなく、前へ前へ突き進んでいけるね。
家族とは久しぶりの当たり前の生活を、穏やかで笑いたっぷりの毎日を過ごせました。再び離れて暮らすけれども、また会うたびに、びっくりしてもらえるくらい豊富な人間関係を基盤として大人になっていきます。お見守りください。
これからも、多くの方に支えていただきながら、もっと多くの人たちの励みや希望となれる人間に成長できるよう、生きていきます。
